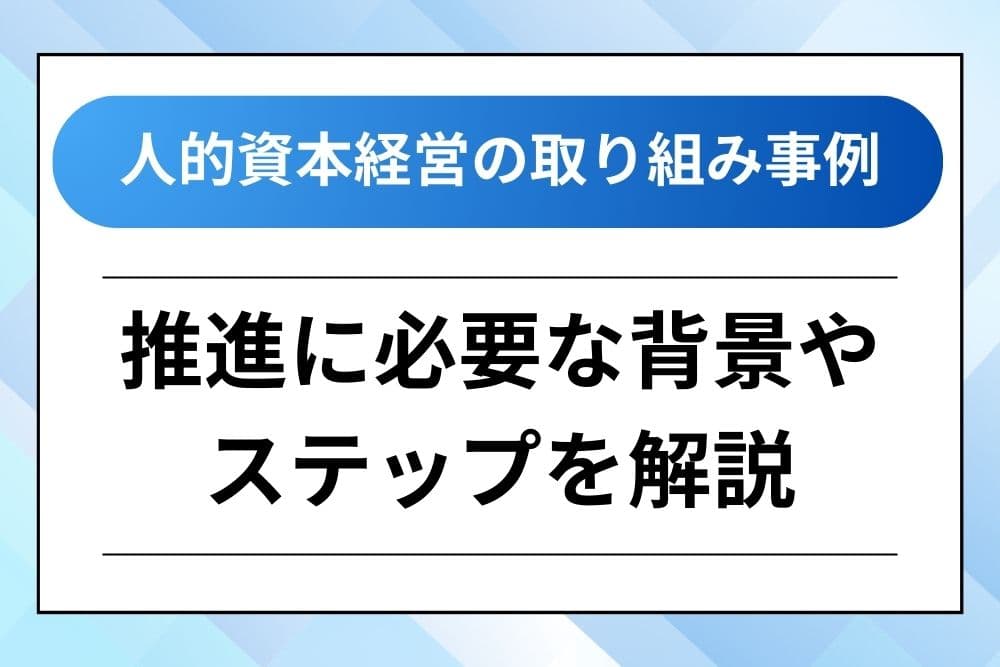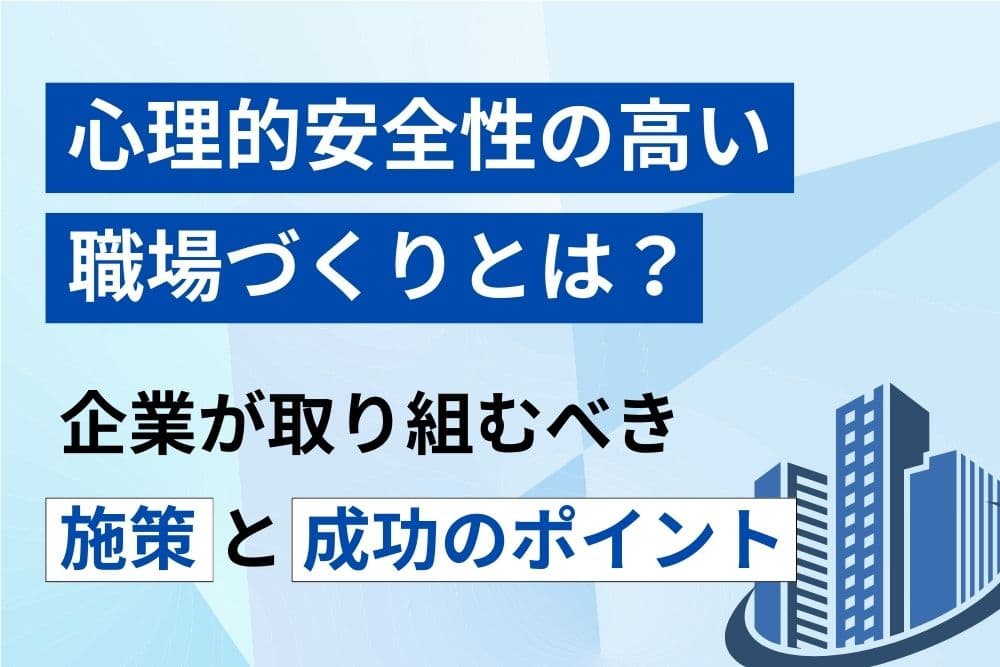お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
組織を強くする「帰属意識」と「エンゲージメント」の違いと高め方
 詳細を見る
詳細を見る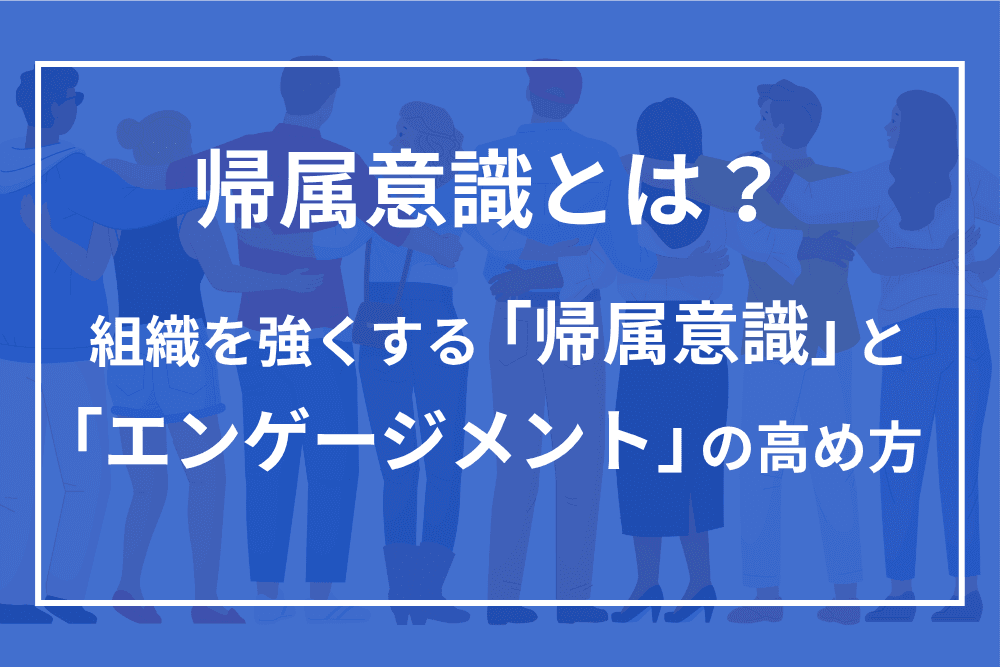
帰属意識とは
エンゲージメントとは
帰属意識とエンゲージメントの相違点
エンゲージメントが重要視される背景
高いエンゲージメントが組織にもたらす効果
企業の成長において、従業員の「帰属意識」と「エンゲージメント」は非常に重要な要素です。これらの概念は混同されがちですが、それぞれ異なる意味合いを持ち、組織に多様な効果をもたらします。
本記事では、帰属意識とエンゲージメントの定義や違い、それぞれの重要性、組織にもたらす効果、そして具体的な高め方について詳しく解説します。帰属意識が低いことによる原因と対処法にも触れ、組織を強くするための考え方を解説します。
目次
帰属意識とは

帰属意識とは、個人がある特定の集団や組織の一員であると感じる意識や感覚を指します。心理学の用語としても用いられ、企業においては従業員が「自分は会社組織の一員である」という自覚を持つことを意味します。
所属する組織への愛着や一体感が強く、組織の目標達成に貢献したいという気持ちや、その組織に所属し続けたいという意識につながります。また、エンゲージメントとは、従業員が会社や組織、あるいは仕事に対して抱くポジティブな結びつきや貢献意欲を指し、帰属意識と関連性の深い概念です。
エンゲージメントとは
エンゲージメントとは、従業員が所属する企業や組織、あるいは自身の仕事に対して感じる積極的な関わりや貢献意欲を指します。これは、単に会社に満足しているという状態とは異なり、組織の目標達成に向けて自発的に貢献したいという内発的な動機付けを含んでいます。
違いとしては、エンゲージメントと帰属意識は共に組織と個人のつながりを示しますが、帰属意識が組織への一体感や愛着といった側面に重点を置くのに対し、エンゲージメントは仕事への主体的な関わりや貢献意欲に重きを置くという点が挙げられます。
帰属意識とエンゲージメントの違い
帰属意識とエンゲージメントは、従業員と組織の関係性を示す言葉としてしばしば一緒に語られますが、その性質には明確な違いがあります。
帰属意識は、従業員が自分が組織の一員であると感じる感覚や、組織に対する愛着や一体感を指し、どちらかというと「組織に所属していたい」という気持ちに焦点が当たります。
一方、エンゲージメントは、従業員が組織の目標達成や事業の成功に向けて積極的に貢献したいという意欲や、仕事そのものへの熱意を示します。
帰属意識が高い従業員は組織に留まる傾向がありますが、必ずしも組織の業績向上に直接的に貢献するとは限りません。対照的に、エンゲージメントが高い従業員は、自身の業務を通じて組織に貢献しようという意識が強く、業績への連動性が高いという特徴があります。
また、帰属意識が従業員から組織への一方的な意識であるのに対し、エンゲージメントは従業員と組織の間の双方向的な関係性を示す言葉として用いられることもあります。
エンゲージメントが重要視される背景
近年、ビジネス環境の急速な変化に伴い、従業員のエンゲージメントが組織の成功に不可欠な要素として強く認識されるようになりました。
終身雇用制度の崩壊や働き方の多様化により、従業員が単に企業に所属するという意識だけでなく、自身のキャリアや働きがいを重視する傾向が強まっています。
持続的な成長を遂げるためには、従業員が会社や仕事に対して主体的な関心と貢献意欲を持つことが不可欠です。
エンゲージ人材の流動性が高まる中で優秀な人材を惹きつけ、定着させるためにも、従業員のエンゲージメントを高めることが多くの企業にとって重要な経営課題となっているのです。
高いエンゲージメントが組織にもたらす効果
従業員のエンゲージメントが高い状態は、組織に対して多岐にわたる好影響をもたらします。従業員が自身の仕事や組織に対して情熱を持ち、積極的に関わることで、組織全体のパフォーマンス向上に繋がる様々な効果が期待できます。
業績・生産性への影響

エンゲージメントの高い従業員は、自身の業務に意欲的に取り組み、目標達成に向けた貢献意欲が強いため、結果として一人ひとりの生産性が向上します。これは個人レベルに留まらず、チーム全体の効率性や創造性の向上にも繋がり、組織全体の生産性アップに貢献します。
厚生労働省の調査からも、ワークエンゲージメントスコアが高いほど労働生産性も向上するという関連性が示されています。また、積極的に業務に取り組む姿勢は、新しいアイデアの創出や業務プロセスの改善にも繋がり、企業の競争力強化に寄与します。
チームワーク・風通しのよい職場環境形成
エンゲージメントが高い状態は、従業員間の積極的なコミュニケーションや協力体制を促進します。組織の目標やビジョンを共有し、共通の目的に向かって働く意識が高まるため、チームの一体感が醸成され、円滑な人間関係が構築されやすくなります。
心理的安全性が高まり、従業員が安心して意見やアイデアを自由に発言できる風通しの良い職場環境が生まれるでしょう。活発な意見交換は、問題解決能力の向上や新たなイノベーションの創出にも繋がり、組織全体の活性化に貢献します。
帰属意識が高いと何が起きるか
従業員の帰属意識が高い状態は、組織に様々な良い影響をもたらします。組織の一員であるという意識が強まることで、従業員の言動に変化が現れ、それが組織全体の活性化に繋がります。
業績・生産性への影響
帰属意識が高い従業員は、組織への愛着や一体感が強いため、
- この会社を支えたい
- 部署のメンバーと協力して業績を上げたい
というように、仕事に対する熱意が高まります。組織の一員としての自覚から、自身の業務が組織全体の目標達成にどのように貢献しているかを意識し、主体的に業務に取り組むようになります。
これにより、個人の生産性が向上するだけでなく、チーム全体の協力体制が強化され、結果として組織全体の業績向上に繋がることが期待できます。
離職率・定着率の改善効果
帰属意識が高い従業員は、所属する組織に愛着を感じているため、長期にわたってその企業で働きたいという気持ちが強くなります。これは離職率の低下に直接的に繋がり、人材の定着率を向上させる効果があります。
人材が安定して定着することで、新たな人材採用や育成にかかるコストや手間を削減でき、既存社員の負担軽減にも繋がります。長く働く従業員が増えることで、組織内に知識や経験が蓄積され、企業の競争力強化にも貢献するでしょう。
チームワーク・風通しのよい職場環境形成
帰属意識が高い従業員が多い組織では、従業員同士の一体感が醸成されやすく、互いに協力し合って仕事に取り組む意識が高まります。組織の一員であるという共通認識が、従業員間のコミュニケーションを活性化させ、信頼関係の構築を促します。
これにより、心理的な安全性が高まり、従業員が自由に意見を交換できる風通しの良い職場環境が生まれます。活発な議論は、課題解決や新しいアイデアの創出に繋がり、組織全体の活性化に貢献します。
帰属意識が低いとどうなるか
従業員の帰属意識が低い状態は、個人だけでなく組織全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。様々な問題が発生し、企業の持続的な成長を阻害する要因となります。
離職リスク・エンゲージメント低下の連鎖
帰属意識が低い従業員は、組織への愛着や一体感を感じにくいため、「この企業で働き続ける理由がない」と感じやすく、転職や離職を検討する可能性が高まります。帰属意識の低下は、仕事へのモチベーション低下にも繋がり、結果としてエンゲージメントも低下する傾向があります。
エンゲージメントの低い状態が続くと、さらに帰属意識が薄れるという負のスパイラルに陥り、組織全体の離職率上昇を招きかねません。優秀な人材の流出は、残された従業員の負担増加や組織力の低下にも繋がります。
低帰属状態が引き起こす職場の問題行動
帰属意識が低い従業員は、組織への貢献意欲が希薄になるため、業務への取り組みが受動的になり、「言われたことだけやればいい」という意識になりがちです。組織内で発生した問題や課題を「自分ごと」として捉えられず、他人事のように考える傾向が見られます。
これは業務効率や生産性の低下を招くだけでなく、無責任な言動や規律の緩みといった問題行動に繋がる可能性もあります。チームワークが損なわれ、従業員間の協力体制が弱まることで、職場の雰囲気が悪化し、心理的な安全性も低下するでしょう。
若手社員に多い傾向とその理由
近年、特に若手社員の間で帰属意識が低い傾向が見られます。これは、終身雇用制度の崩壊や働き方の多様化が進み、一つの企業に長く勤めることへの価値観が変化していることが背景にあります。
若手社員は、自身の成長やキャリア形成、プライベートの充実を重視する傾向が強く、企業のビジョンや価値観への共感が得られない場合や、自身の役割やキャリアパスが不明確な場合に、帰属意識を持ちにくくなります。
また、リモートワークの普及により、同僚や上司との物理的な距離が離れ、人間関係が希薄になることも、帰属意識の低下に影響を与えていると考えられます。
帰属意識を高める具体的な施策
従業員の帰属意識を高めるためには、組織として意図的な働きかけを行うことが重要です。多角的なアプローチを通じて、従業員が組織の一員であることを実感し、愛着を持てるような環境を整備する必要があります。
ビジョンや理念の浸透
企業のビジョンや理念を従業員に明確に伝え、共感を促すことは、帰属意識を高める上で非常に効果的です。従業員が自身の仕事が会社の目指す方向とどのように繋がっているのかを理解することで、仕事への意義ややりがいを感じやすくなります。
社内報や動画、ワークショップなどを活用し、繰り返し発信することで、企業文化や価値観の浸透を図りましょう。全員が共通の目標を持つことで、組織としての一体感が生まれます。
コミュニケーションの機会を設ける

従業員同士が気軽にコミュニケーションを取れる機会を増やすことも、帰属意識の向上に繋がります。上司や同僚との良好な人間関係は、従業員が組織に居場所を感じる上で重要です。
シャッフルランチや部活動、社内イベントなどを企画することで、部署を越えた交流を促進し、相互理解を深めることができます。また、チャットツールや社内SNSなどを活用し、日常的なコミュニケーションを活性化することも有効です。
組織文化や風土の整備
従業員が安心して働ける、風通しの良い組織文化や風土を醸成することも重要です。心理的安全性が確保された環境では、従業員は自分の意見を自由に発言でき、失敗を恐れずに新しいことに挑戦できます。
多様な働き方を受け入れたり、従業員のワークライフバランスを尊重したりすることも、従業員の満足度と帰属意識を高めることに繋がります。
評価制度・処遇の公平性
従業員の努力や成果が正当に評価され、それが処遇に反映される透明性の高い評価制度は、帰属意識を高める上で不可欠です。評価基準を明確にし、公平な運用を徹底することで、従業員は「自分は会社に貢献できている」「適切に評価されている」と感じ、組織への信頼感を高めます。
給与や福利厚生の見直しも、従業員の満足度と帰属意識の向上に効果的です。
社内イベント・オフサイトミーティングの効果
社内イベントやオフサイトミーティングは、従業員同士の非公式な交流を促進し、人間関係を強化する効果があります。部署や役職を超えた交流を通じて、互いの人となりを知り、親近感を持つことで、組織全体の一体感が生まれます。
リラックスした雰囲気の中での交流は、心理的な距離を縮め、よりオープンなコミュニケーションを促すでしょう。
帰属意識が低い原因と対処法
従業員の帰属意識が低い状態には、様々な要因が考えられます。これらの原因を特定し、適切な対処を行うことが、帰属意識を高めるための第一歩となります。
管理職の意識不足
管理職が従業員の帰属意識の重要性を理解していない場合や、部下とのコミュニケーションを十分に取れていない場合、従業員の帰属意識が低下することがあります。管理職は、部下との信頼関係を築き、個々の貢献を認め、キャリアをサポートする役割を果たす必要があります。
管理職向けの研修などを実施し、部下育成やコミュニケーションスキル向上のためのサポートを行うことが重要です。
評価・報酬への不満
自身の仕事が適切に評価されていないと感じる場合や、報酬に不満がある場合、従業員の帰属意識は低下します。努力や成果が正当に評価されていないと感じると、「会社に必要とされていない」という感覚を抱きやすくなります。
透明性のある評価制度を導入し、従業員が納得できる評価と報酬体系を構築することが不可欠です。定期的なフィードバックの機会を設け、従業員の貢献を具体的に伝えることも効果的です。
個人主義的な社風
組織全体として個人主義的な傾向が強く、従業員間の協力やチームワークが重視されない社風も、帰属意識の低下に繋がることがあります。従業員が孤立感を感じやすく、組織の一員であるという感覚を持ちにくくなります。
チームでの目標達成を奨励したり、部署を越えた交流を促進したりするなど、協調性を育むための施策を講じることが重要です。
キャリアパスの不透明さ
企業内での自身のキャリアの方向性や、将来の成長機会が不明確な場合も、従業員の帰属意識は低下しやすくなります。従業員は「この会社で働き続ける意味があるのか」と疑問を感じ、他の企業に目を向ける可能性があります。
定期的なキャリア面談を実施し、従業員のキャリア志向を把握した上で、社内でのキャリアパスを示すことが重要です。研修制度や資格取得支援などを充実させ、従業員の成長をサポートする体制を整えましょう。
社員の声を拾いきれていない体制
従業員が会社に対して意見や要望を伝えにくい環境や、伝えたとしてもそれが組織運営に反映されないと感じる場合、従業員の会社への信頼感や帰属意識は低下します。従業員は「自分の声は聞いてもらえない」と感じ、組織への関心を失いやすくなります。
定期的な従業員サーベイや目安箱の設置、タウンホールミーティングなどを通じて、従業員の声を収集し、可能な範囲で組織運営に反映させる姿勢を示すことが重要です。
中小企業・スタートアップがとるべき戦略
中小企業やスタートアップは、大企業に比べてリソースが限られている場合が多いですが、帰属意識を高めるための独自の強みを活かすことができます。限られたリソースの中でも効果的に帰属意識を高めるための戦略を検討しましょう。
限られたリソースで高めるには?
中小企業やスタートアップでは、大規模な研修プログラムや福利厚生制度の充実は難しい場合があります。しかし、コストをかけずに帰属意識を高める方法はいくつかあります。
例えば、経営層が積極的に従業員とコミュニケーションを取り、企業のビジョンや想いを直接伝えることは、従業員の共感と一体感を生み出すために非常に効果的です。
また、少人数であることを活かした、より密なチームワークの促進や、従業員一人ひとりの貢献を具体的に認め、称賛する文化を醸成することも、帰属意識の向上に繋がります。
経営層と従業員の距離感を活かす
中小企業やスタートアップは、経営層と従業員の物理的・心理的な距離が近いという利点があります。この距離感を活かし、経営層が従業員一人ひとりと積極的に関わることで、従業員は「自分は会社の重要な一員である」という意識を持ちやすくなります。
経営課題や目標についてオープンに話し合ったり、従業員の意見やアイデアを積極的に取り入れたりすることで、従業員の参画意識を高め、帰属意識を醸成することができます。
オンボーディングと日常の声かけの重要性
社員オンボーディングとは、新入社員が組織文化や業務に迅速に順応し、早期に成果を出せるよう支援する一連の受け入れプロセスです。
中小企業やスタートアップにおいて、新入社員のオンボーディングは特に重要です。企業文化やビジョンを丁寧に伝え、チームに馴染めるようなサポートを行うことで、早期に帰属意識を醸成することができます。
また、日々の業務の中での上司や同僚からの声かけや、感謝の気持ちを伝え合う文化も、従業員の帰属意識を高める上で効果的です。小さなコミュニケーションの積み重ねが、従業員の安心感や一体感に繋がり、「ここにいて良いんだ」という感覚を育みます。
帰属意識を高める際の注意点
帰属意識を高める取り組みは組織にとって重要ですが、その進め方によっては逆効果になる可能性もあります。従業員の多様性を尊重し、無理のない形で進めることが成功の鍵となります。
やりすぎ・押し付けのリスク
帰属意識の向上を過度に強調したり、従業員に一方的に愛社精神を押し付けたりすることは避けるべきです。従業員が「〇〇しなければならない」と感じてしまうと、かえって組織への反発や不信感を生む可能性があります。
帰属意識は、あくまで従業員の内発的な感情や自発的な意思に基づいて醸成されるべきものであり、強制されるべきではありません。
表面的な取り組みがもたらす弊害
形だけの社内イベントや、目的が不明確なコミュニケーション施策など、表面的な取り組みは従業員に見透かされてしまい、逆効果となることがあります。従業員は「会社は本気で私たちのことを考えていないのではないか」と感じ、不信感を抱く可能性があります。
帰属意識を高めるためには、従業員のニーズや組織の課題をしっかりと把握し、本質的な課題解決に繋がる施策を計画・実行することが重要です。
多様性を尊重したアプローチの必要性
働き方や価値観が多様化している現代において、一律の施策で全ての従業員の帰属意識を高めることは困難です。個々の従業員のバックグラウンドやキャリア志向、ライフスタイルなどを理解し、それぞれのニーズに合わせた柔軟なアプローチが求められます。
多様な働き方を選択できる制度を導入したり、個別のキャリア支援を行ったりするなど、従業員一人ひとりが「自分はこの組織で認められている」と感じられるような環境整備が重要です。
時間連動型の賃金制度
時間連動型の賃金制度は、必ずしも帰属意識の低下に直結するわけではありませんが、成果や貢献度が給与に反映されにくいと感じる従業員にとっては、モチベーションや帰属意識を低下させる要因となる可能性があります。
従業員が自身の働きが正当に評価されていると感じられるような、透明性のある評価制度と連動した報酬体系を検討することが重要です。
過度な法令順守
法令順守は企業の存続にとって不可欠ですが、過度に厳格なルールや形式的な手続きは、従業員の自律性や創造性を阻害し、組織の硬直化を招く可能性があります。従業員が息苦しさを感じ、組織への愛着を持ちにくくなることも考えられます。
法令順守を徹底しつつも、従業員が柔軟に働けるような環境を整備し、心理的な安全性を確保することが重要です。帰属意識とエンゲージメントは、従業員が組織に対してポジティブな感情を持ち、主体的に貢献する上で相互に関連する要素であり、バランスの取れた施策が求められます。
まとめ
本記事では、組織を強くする上で重要な「帰属意識」と「エンゲージメント」について、それぞれの定義や違い、組織にもたらす効果、そして具体的な高め方や注意点について解説しました。帰属意識だけに依存すると組織は内向き・保守的になり、成長が停滞しかねません。
むしろ成果と待遇の好循環を生む高いエンゲージメントが先に確立されれば、後から自然と帰属意識も醸成されます。
まずはエンゲージメントを可視化し、向上施策を成果・報酬へ直結させるフローを設計し、その上で「貢献 → 評価 → 処遇向上」という循環を回し続ければ、従業員は自発的に組織へのロイヤルティを深めます。
高い帰属意識とエンゲージメントは、業績向上や離職率の低下、良好な人間関係の構築に繋がり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。従業員の帰属意識を高めるためには、企業のビジョンや理念を浸透させ、コミュニケーションを活性化し、公平な評価制度を整えるなど、多角的なアプローチが必要です。
本記事で紹介した施策を参考に、貴社の組織文化や従業員の状況に合わせた取り組みを進めることで、より強くエンゲージメントの高い組織を作り上げていきましょう。


- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。