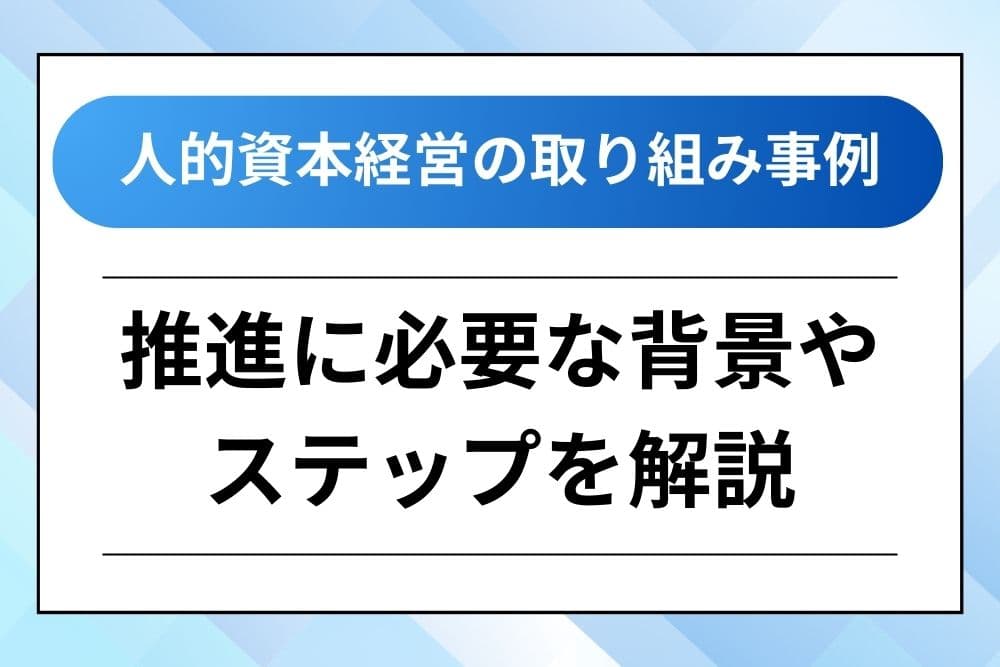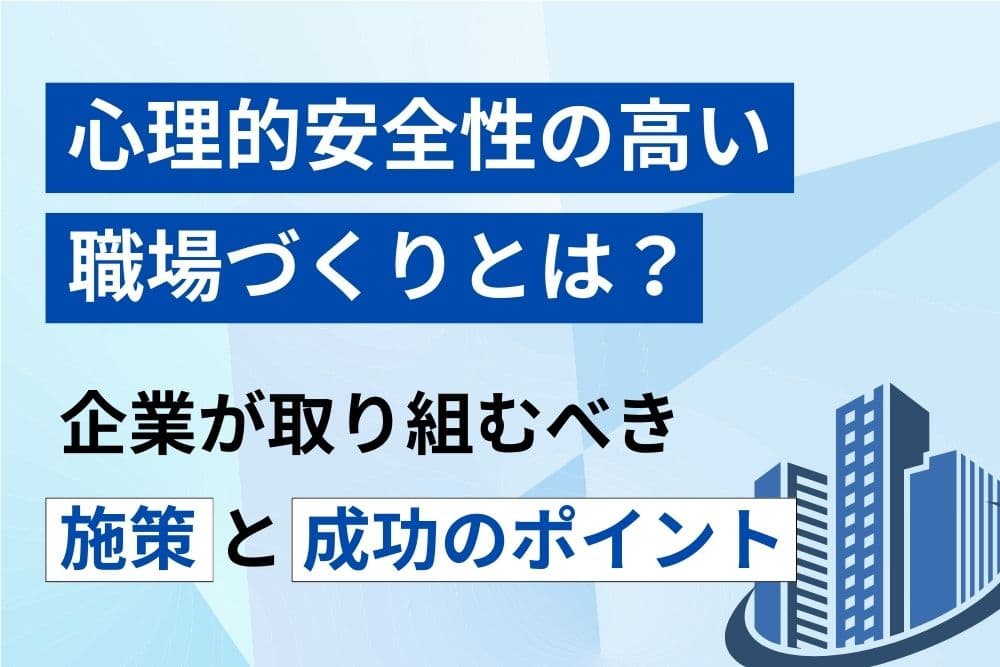お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
日本の金融リテラシーは世界で何位?企業が知っておくべき現状と対策
 詳細を見る
詳細を見る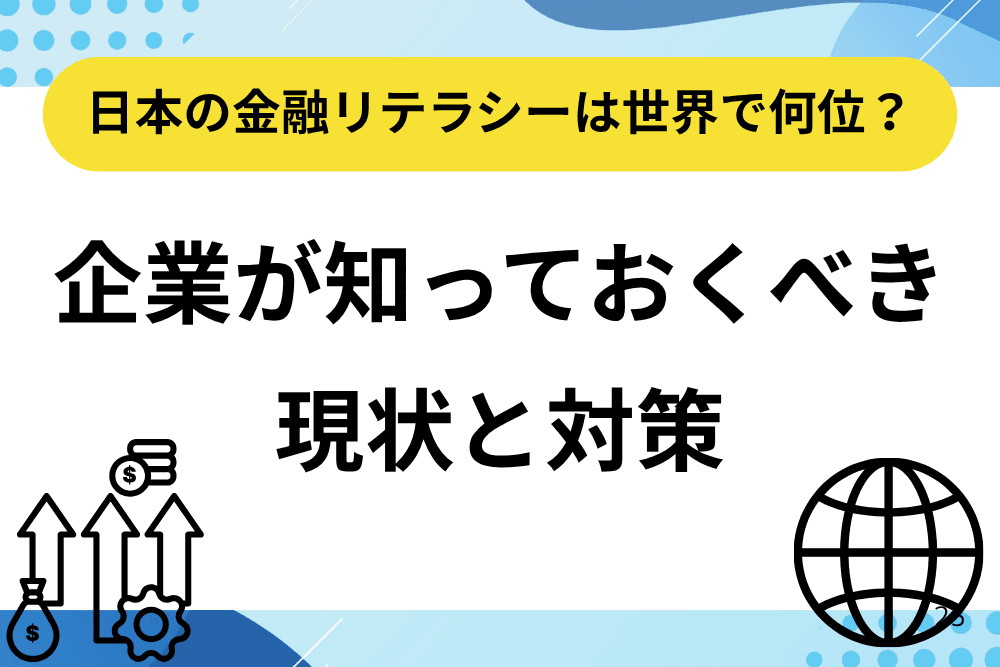
日本の金融リテラシーの現状と国際比較
金融リテラシーが企業に与える影響
なぜ日本は金融リテラシーが低いのか
企業での金融リテラシー教育の必要性と方法
金融教育を導入した企業の具体例
企業の経営者や人事担当者の皆様にとって、従業員の金融リテラシーは単なる個人の問題ではなく、企業のパフォーマンスやリスク管理にも直結する重要な経営課題です。
本記事では、日本の金融リテラシーの現状を国際比較を交えながら解説し、その低さが企業に与える影響、そして企業が従業員の金融リテラシー向上にどのように取り組むべきかについて具体的な方法や事例を交えてご紹介します。
目次
日本の金融リテラシーの現状と国際比較
日本の金融リテラシーは国際的に見てどのような位置にあるのでしょうか。最新の調査結果や他国との比較から、日本の金融教育の現状と課題が見えてきます。
最新の調査結果と日本のランキング
金融広報中央委員会が実施した「金融リテラシー調査2022年」の結果によると、日本の金融知識に関する設問の正答率は、主要国である英国、ドイツ、フランスのいずれにも及ばなかったという結果が報告されています。
また、過去の調査では、アメリカの有力格付け会社スタンダード・アンド・プアーズが2015年に実施した「グローバル・ファイナンシャル・リテラシー調査」において、日本はG7の中で6位、世界では38位という結果でした。
特に「インフレ」「複利」「分散投資」といった資産運用において重要な分野での理解度が低い現状が明らかになっています。若年層を含む多くの日本人にとって、金融リテラシーは依然として向上の余地が大きいと言えるでしょう。
他国との比較から見える教育ギャップ
日本の金融教育は、海外と比較すると遅れが指摘されています。金融広報中央委員会の調査によると、金融教育を学校等で受けた人の割合は、米国が20%であるのに対し、日本はわずか7%に留まっています。
こうした教育機会の少なさが、金融知識への自信の低さにも繋がっており、米国で金融知識に自信がある人が71%に上るのに対し、日本は12%となっています。また、高校での金融教育は2022年度から義務化されましたが、教員側の専門知識不足や授業時間の確保が課題となっています。
特に若年層に対する実践的な金融教育において、他国との教育ギャップが見られます。
金融リテラシーが企業に与える影響
従業員の金融リテラシーの現状は、個人の問題に留まらず、企業の経営にも様々な影響を及ぼします。特に日本人の金融リテラシーが低い現状は、企業にとって無視できない課題と言えるでしょう。
従業員の金銭理解が業務効率・判断力に直結する

OECDの調査等で日本人の金融リテラシーが比較的低い現状が示されています。従業員が自身の家計や資産状況を適切に管理できていない場合、金銭的な不安を抱えやすくなり、それが業務への集中力の低下やモチベーションの低下につながる可能性があります。
また、ビジネスの現場においても、契約内容の理解や経費精算、福利厚生制度の活用など、金銭に関する正確な理解が求められる場面は多々あります。金融リテラシーが低い従業員は、これらの場面で適切な判断が難しくなり、業務効率の低下やミスを引き起こすリスクが高まります。
社員の経済的ストレスの軽減が職場に好影響を及ぼす
OECDの調査などでも指摘されているように、日本人の金融リテラシーは低い現状にあります。経済的な不安は、従業員の心身の健康に影響を与え、ストレスの原因となります。
借金の問題や将来への漠然としたお金の不安は、従業員のエンゲージメントや生産性を低下させる要因となり得ます。
企業が従業員の金融リテラシー向上を支援し、経済的なストレスを軽減することで、従業員は安心して業務に取り組むことができるようになります。これにより、職場の雰囲気改善や従業員満足度の向上、ひいては離職率の低下にも繋がることが期待されます。
なぜ日本は金融リテラシーが低いのか
日本の金融リテラシーが低い現状には、複数の要因が複合的に影響しています。
学校教育が不十分
長らく日本の学校教育では、お金に関する実践的な教育が十分に行われてこなかったという歴史があります。限られた授業時間の中で多岐にわたる科目を扱う必要があり、金融に関する内容は深く掘り下げられることが少なかったのが現状です。
2022年度から高校家庭科で金融教育が必修化されましたが、これまでの金融教育を受けていない社会人が多い現状を踏まえると、学校教育だけでは国民全体の金融リテラシーを向上させるには時間がかかります。教える側の教員の金融知識にばらつきがある点も課題として指摘されています。
家庭での金銭教育が不十分
日本では、家庭内でお金についてオープンに話す文化があまり根付いていないという現状があります。親自身がお金に関する知識に自信がなかったり、お金の話を子供にすることを避けたりする傾向が見られます。
そのため、子供がお金の使い方や貯蓄、投資などについて家庭で学ぶ機会が少なく、基本的な金銭感覚やライフプランニングの重要性を理解する機会が不足しがちです。
社会全体に漂う「お金は話題にすべきでない」風潮
日本では古くから、お金の話をすることを「はしたない」「品がない」とする社会的な風潮がありました。このため、お金に関する知識を得たり、疑問点を質問したりすることに抵抗を感じる人が少なくありません。
このような意識は、金融に関する学びの機会を自ら求めることを妨げ、結果として金融リテラシーが向上しにくい現状を生み出しています。社会全体でお金についてオープンに話し合える環境づくりが必要です。
企業での金融リテラシー教育の必要性と方法
日本人の金融リテラシー向上は喫緊の課題であり、企業がその一翼を担うことの重要性が高まっています。企業が従業員向けに金融教育を実施することは、従業員個人のメリットに加えて、企業にとっても様々なメリットをもたらします。
社内研修・eラーニングによるベース知識の普及
企業が従業員の金融リテラシー向上に取り組む第一歩として、社内研修やeラーニングを活用した金融に関する基礎知識の普及が効果的です。
- 家計管理
- 貯蓄や投資
- 保険やローンの仕組み
- 税金
- 社会保障制度に関する基本的な知識
など、従業員が日常生活で直面するお金に関するトピックスを網羅したコンテンツを提供します。
eラーニングであれば、従業員は自身のペースで学ぶことができ、時間や場所を選ばずにアクセスできるため、多忙な業務の合間でも学習を進めやすいという利点があります。
定期的なワークショップと社内講師制度の活用
一方通行の知識伝達だけでなく、従業員がアクティビティに参加できるワークショップ形式の研修も有効です。具体的なライフプランニングや資産形成のシミュレーションなどを通じて、学んだ知識を実践に落とし込むトレーニングを行います。
また、社内に金融に関する知識や経験を持つ従業員がいる場合は、社内講師として登壇してもらうことも検討できます。身近な存在である同僚からの話は、従業員にとってよりリアリティを持ち、学習へのモチベーション向上に繋がる可能性があります。
ライフステージ別教育(新卒・中堅・管理職)での応用
従業員の金融に関するニーズは、ライフステージによって変化します。新卒社員には、給与明細の見方や社会保険、税金の基本、一人暮らしの家計管理など、社会人として最低限知っておくべきお金の知識を中心に教育します。
30代から40代の中堅社員には、結婚や出産、住宅購入など、ライフイベントに合わせた資金計画や資産形成の方法、各種ローンの活用など、より実践的な内容に焦点を当てます。
50代以上の管理職層には、リタイアメントプランニング、年金制度の詳細、相続・贈与に関する知識など、老後に向けた準備に関する内容を提供するなど、それぞれのライフステージに応じた計画的な教育プログラムを設計することが重要です。

金融教育を導入した企業の具体例
実際に金融教育を導入している企業では、様々な取り組みが行われており、その効果も現れています。ここでは、いくつかの具体例を紹介します。
社内投資講座で社員のNISA利用率が倍増(※家計安定)
ある企業では、従業員の資産形成を支援するために、社内で投資に関する講座を定期的に開催しています。
NISAやつみたてNISAなどの非課税制度の仕組みや活用方法、分散投資の重要性などについて専門家を招いて分かりやすく解説することで、これまで投資に縁がなかった従業員も興味を持つようになりました。
その結果、社内でのNISA利用率が導入前に比べて倍増し、従業員が将来の老後資金作りや将来の資産構築に向けた一歩を踏み出すきっかけとなっています。
管理職向けマネープラン研修(※従業員満足度が向上し離職率が20%改善)
別の企業では、管理職向けに特化したマネープラン研修を実施しています。管理職は自身のライフプランニングに加え、部下のキャリアや生活に関する相談を受けることもあります。
この研修では、自身の資産形成の知識を深めるとともに、部下からの相談にも適切に対応できるよう、幅広い金融知識を習得します。
研修参加者からは、「将来への漠然とした不安が解消された」「部下とのコミュニケーションの質が向上した」といった声が聞かれ、従業員全体の満足度向上に繋がり、結果として離職率が20%改善されるという効果が見られました。
社内副業支援と金融教育の組み合わせ(※社員の意識が変わり、実際に新しい仕事を生み出す動きが増えた)
ある先進的な企業では、社員の自律的なキャリア形成を支援するため、社内副業制度を導入するとともに、副業で得た収入の管理や、将来の資産形成を見据えた金融教育をセットで提供しています。
単に副業を推奨するだけでなく、得た収入をどのように活かすかを考える機会を与えることで、社員のお金に対する意識が変化しました。
自己投資や資産運用に関心を持つ社員が増え、それがモチベーションとなり、結果的に社内外で新しい仕事やプロジェクトを生み出す動きが増えるという波及効果が生まれています。
金融リテラシー向上のためのステップガイド
従業員の金融リテラシー向上を成功させるためには、計画的かつ継続的な取り組みが必要です。以下のステップを参考に、自社に合った金融教育プログラムを導入しましょう。
現状把握(社員アンケート・知識レベルテスト)
まず、従業員の金融リテラシーの現状を把握することが重要です。社員アンケートや金融知識レベルテストを実施し、従業員がどのようなお金の知識を持ち、どのような点に不安や関心があるのかを測定します。
これにより、教育が必要な内容や対象となる従業員層を明確にすることができます。アンケートでは、個人の資産状況や収入・支出に関する詳細な情報を聞き出すのではなく、金融に関する一般的な知識や関心事、教育へのニーズなどを尋ねるのが良いでしょう。
課題ごとのカリキュラム設計と学習導線の設計
現状把握の結果に基づき、従業員の金融リテラシーの課題に合わせたカリキュラムを設計します。例えば、若い世代は資産形成に関心が高い一方で基本的な家計管理が苦手な傾向があるかもしれません。逆に、高齢層は相続や終活に関する知識を求めているかもしれません。
それぞれの課題に対応した研修内容や形式(集合研修、eラーニング、個別相談など)を組み合わせ、従業員が無理なく学習を進められるような設計にします。必要に応じて外部の専門機関やファイナンシャルプランナーと連携することも有効です。
教育実施と定期的な評価サイクルの導入

設計したカリキュラムに沿って金融教育を実施します。一度きりの研修で終わらせるのではなく、定期的にフォローアップの機会を設けたり、eラーニングの進捗状況を確認したりすることが効果的です。
また、教育の効果を測定するために、研修前後での知識レベルの変化をテストしたり、アンケートで従業員の意識や行動の変化を計測したりします。
これらの評価結果を次の教育プログラムの改善に活かすというPDCAサイクルを回すことで、より効果的な金融教育へと繋げることができます。
企業が金融リテラシー向上に取り組む意義と展望
企業が従業員の金融リテラシー向上に取り組むことは、単なる福利厚生の充実に留まらず、企業の持続的な成長に不可欠な要素となります。
経済的な安定が企業の競争力につながる
従業員一人ひとりの経済的な安定は、企業全体の競争力向上に直結します。
経済的な不安が軽減された従業員は、業務に集中し、生産性を高めることができます。また、将来への経済的な影響は、従業員のエンゲージメントを高め、企業への帰属意識を醸成します。
優秀な人材の定着にも繋がり、結果として企業の持続的な成長を支える強固な基盤となります。
企業全体で取り組む、お金の知識づくり
金融リテラシーの向上は、一部の部署や個人の努力だけでなく、企業全体で取り組むべき課題です。経営層が金融教育の重要性を理解し、積極的に推進することで、従業員も安心して学習に取り組める環境が形成されます。
社内報やイントラネットを活用した情報提供、金融に関する相談窓口の設置など、企業全体でお金の知識づくりを支援する仕組みを構築することが望まれます。
社員の成長に投資することで会社も伸びる
金融リテラシー教育は、従業員への投資です。従業員がお金の知識を身につけ、自身の人生をより豊かにデザインできるようになることは、働くモチベーションの向上に繋がります。
従業員が経済的な安定を得て、将来に対するポジティブな展望を持てるようになれば、自律的にキャリアを形成し、新しいスキルを習得するなど、さらなる成長を目指すようになります。
社員の成長は企業の成長に繋がり、企業価値の向上にも貢献するでしょう。

まとめ
日本の金融リテラシーは国際的に見て改善の余地があり、その現状は企業の経営にも少なからず影響を与えています。従業員の金融リテラシーが低いことは、業務効率の低下や経済的なストレスによるパフォーマンス低下、そして優秀な人材の流出リスクにも繋がりかねません。
企業が従業員向けに金融教育を提供することは、従業員の経済的な安定を支援し、エンゲージメントや生産性を向上させるだけでなく、企業の競争力強化にも貢献する重要な経営戦略となります。
社内研修やeラーニング、ワークショップなどを活用し、従業員のライフステージに合わせた教育プログラムを導入することで、企業全体の金融リテラシーを高め、持続的な成長を目指しましょう。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。