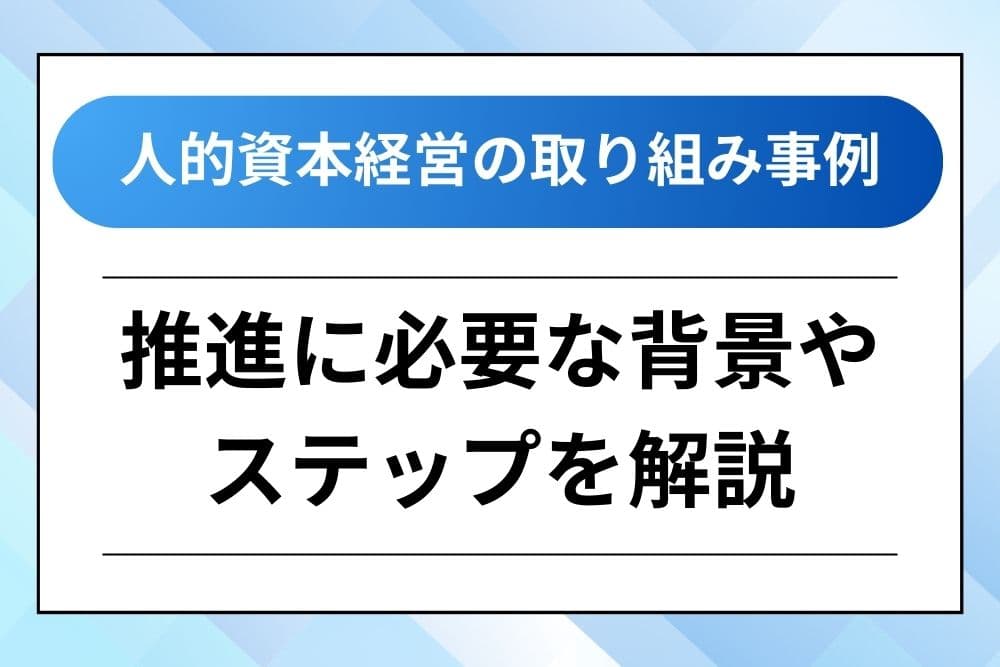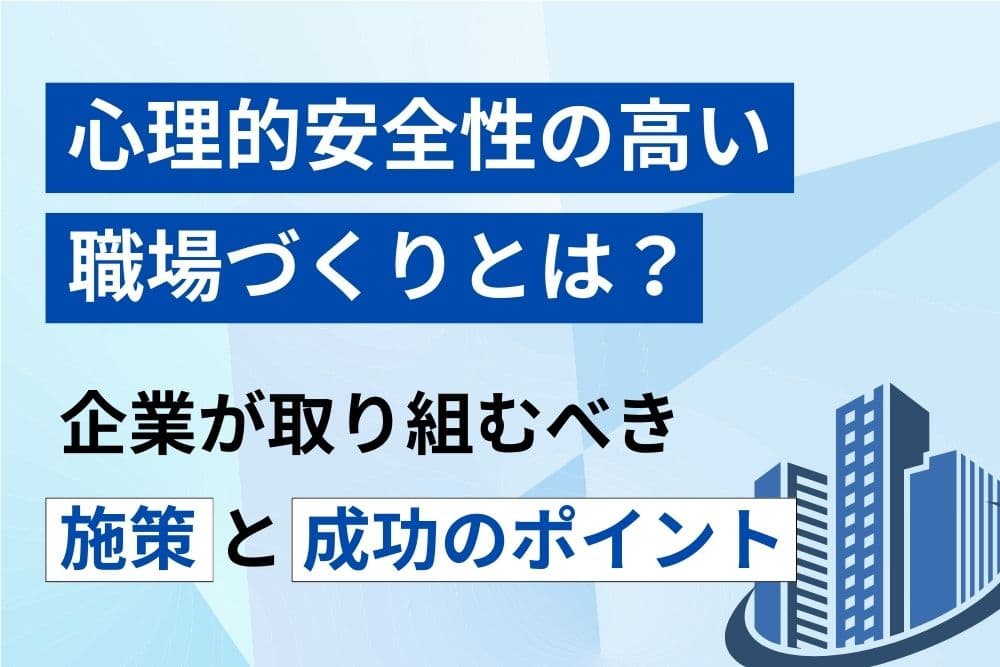お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
なぜ日本では金融教育が遅れているのか?企業が取り組むべき理由と方法
 詳細を見る
詳細を見る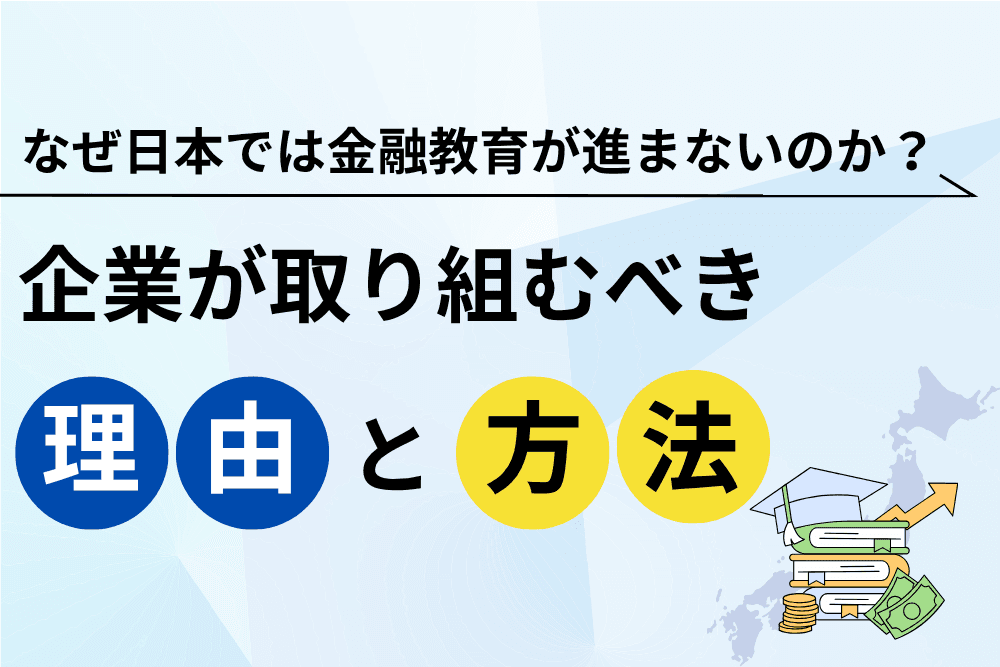
日本の金融教育の現状
金融教育が進まない主な理由
企業が金融教育に取り組む必要性
企業内での金融教育の導入方法
従業員の声:金融教育を受けての変化
日本では金融教育の重要性が叫ばれる一方で、その現状は十分とは言えず、多くの課題を抱えています。個人の資産形成や生活設計、さらには企業の持続的な成長にとっても、金融リテラシーの向上は不可欠です。
本記事では、日本の金融教育が進まない理由を深掘りし、企業が積極的に金融教育に取り組むべき理由や具体的な導入方法について解説します。
目次
日本の金融教育の現状
日本の金融教育は、2005年が「金融教育元年」と位置づけられ、取り組みが始まりました。2022年には学習指導要領が改訂され、高校での金融教育が義務化されるなど、法的な側面での整備は進められています。
しかし、現状として、学校で金融教育を受けたという認識を持つ人は少ないのが実態です。
学校における金融教育の取り組み
学校における金融教育は、文部科学省が定める学習指導要領に基づいて行われます。金融広報中央委員会によるプログラムでは、小学校から高等学校までの金融教育を4つの分野に分けて学習内容を定めています。
主な内容としては、
- 資金管理と意思決定
- 貯蓄の意義と資産運用
- 生活設計、事故・災害・病気などへの備え
- お金や金融の働き
- 経済把握
- 経済変動と経済政策
- 経済社会の諸課題
- 自立した消費者
- 金融トラブル・多重債務
などが挙げられます。
小学校では金銭教育、中学校では消費生活、高等学校の家庭科では家計管理や資産形成について学びます。しかし、授業時間の確保や教員の専門知識不足、受験科目ではないことなどが課題として挙げられています。
社会人の金融リテラシーの実態
金融広報中央委員会が実施した2022年の金融リテラシー調査によると、学校で金融教育を受けたという認識のある人は約7%にとどまっています。これは米国の20%と比較しても低い水準です。
社会人においても、職場で金融教育を受けた経験がない人が多く、体系的な金融知識を習得する機会が限られている現状があります。
この金融リテラシーの不足は、個人の資産形成の遅れや金融トラブルに巻き込まれるリスクを高める要因となります。
金融教育が遅れている背景
日本で金融教育が遅れている背景にはいくつかの要因があります。まず、文化的にお金に関する話題が避けられる傾向があることが挙げられます。また、学校教育においては、金融教育に充てられる授業時間が限られており、教員の専門知識にもばらつきが見られます。
さらに、海外と比較して、金融商品に対する日本人の消極的な姿勢も、金融教育の必要性を感じにくい要因の一つと考えられます。
金融教育が進まない主な理由
日本の金融教育が進まない背景には、文化的な側面や教育現場の課題、そして金融商品に対する国民の意識など、様々な要因が複合的に絡み合っています。これらの理由が、金融教育の普及を妨げる要因となっています。
お金に関する話題が避けられる傾向
日本では、古くからお金に関する露骨な話をすることが「はしたない」「品がない」といった感覚があり、お金について公に話すことが避けられる傾向があります。
このような文化的背景が、家庭内や学校、職場といった様々な場面でお金に関する実践的な知識を学ぶ機会を減少させている一因と考えられます。
お金は生活に不可欠なものであるにも関わらず、その性質上タブー視される風潮が、金融リテラシーの向上を阻害していると言えるでしょう。
学校での金融教育における課題
学校教育における金融教育は、2022年度からの高校での必修化など、前進は見られますが、多くの課題に直面しています。学習指導要領の改訂により内容は拡充されたものの、教員側の金融知識や指導スキルの不足が指摘されています。
また、金融教育に割くことができる授業時間が限られていることや、金融教育が受験科目ではないため生徒の学習意欲が向きにくいといった点も課題として挙げられています。
外部講師の活用や、教員向けの研修の充実といった対策が進められていますが、学校現場での定着には時間を要する現状があります。
金融商品に対する日本人の消極的な姿勢
日本人は、海外の主要国と比較して、預貯金の割合が高く、株式や投資信託といったリスク性金融商品への投資に消極的な傾向が見られます。
この背景には、「損をする可能性」への懸念や、金融・投資に関する知識への自信のなさ、「価格変動に神経を使いたくない」といった意識があると考えられます。
また、過去のバブル経済とその崩壊の経験も、リスク資産への投資に慎重な姿勢を助長している可能性があります。このような金融商品に対する消極的な姿勢は、金融教育の必要性を身近に感じにくくさせている現状に繋がっています。
企業が金融教育に取り組む必要性
企業が従業員に対して金融教育を提供することは、単なる福利厚生の拡充にとどまらず、企業の持続的な成長と従業員のエンゲージメント向上に不可欠な要素となりつつあります。経済的な安定は従業員の安心感に繋がり、それが仕事への集中力や生産性の向上に寄与するためです。
また、企業が従業員のライフプラン形成を支援することは、社会的な責任を果たすことでもあり、企業のブランド価値向上にも繋がります。
従業員の生活安定と生産性向上
従業員が経済的な不安を抱えていると、仕事に集中できず、結果として生産性の低下を招く可能性があります。金融教育によって、従業員が自身の収入や支出を適切に管理し、将来に向けた資産形成やライフプランを具体的に描けるようになれば、経済的な安心感を得ることができます。
この安心感が、業務への集中力やモチベーションを高め、結果として生産性の向上に繋がるのです。企業が従業員の生活安定を支援することは、巡り巡って企業の業績向上に貢献することになります。
企業の社会的責任とブランド価値の向上
企業が従業員の金融リテラシー向上を支援することは、企業の社会的責任(CSR)の一環としても位置づけられます。従業員の経済的な健全性をサポートすることは、単に個人の問題として捉えるのではなく、社会全体の金融リテラシー向上に貢献する取り組みと言えます。
このような従業員を大切にする姿勢は、企業イメージの向上やブランド価値の向上にも繋がり、優秀な人材の採用においても有利に働く可能性があります。
離職率の低下と人材の定着

福利厚生の充実や、従業員のキャリア形成支援は、人材の定着率向上に大きく寄与します。金融教育は、従業員が自身の将来設計を具体的に考える上で非常に役立ち、企業がそのサポートを提供することで、従業員は会社への帰属意識やエンゲージメントを高めることが期待できます。
経済的な不安が軽減され、将来への見通しが立てられるようになれば、他の企業への転職を考える可能性も低くなるでしょう。特に若い世代は、資産形成や金融リテラシー教育の機会がある企業を魅力的に感じる傾向があり、採用力の強化にも繋がります。
企業内での金融教育の導入方法
企業が金融教育を導入する際には、やみくもに行うのではなく、従業員のニーズを把握し、明確な目標を設定することが重要です。その上で、自社の状況に合った教育プログラムを選択し、効果測定と改善を継続的に行うことで、より効果的な金融教育を実現できます。
ニーズの把握と目標設定
企業内で金融教育を導入するにあたり、まず従業員がどのような金融知識や情報に関心があるのか、どのような点に不安を感じているのかといったニーズを正確に把握することが不可欠です。
アンケート調査や個別面談などを通じて、従業員の金融リテラシーの現状や関心事を把握し、それを基に金融教育を通じて達成したい具体的な目標を設定します。
例えば、
- 従業員のiDeCo加入率を〇%向上させる
- 住宅ローンに関する従業員の疑問を〇%解消する
など、定量的かつ測定可能な目標を設定することで、教育プログラムの内容や効果測定の方法を具体的に検討できるようになります。
教育プログラムの選び方とカスタマイズ
ニーズと目標が明確になったら、それに合った教育プログラムを選択します。外部の専門機関が提供する研修プログラムやオンラインコンテンツ、社内講師によるセミナーなど、様々な選択肢があります。
重要なのは、一方的な知識提供だけでなく、従業員が主体的に考え、行動できるよう促す内容であることです。
また、画一的なプログラムではなく、従業員の年代やライフステージ、役職などに応じて内容をカスタマイズすることも効果的です。
例えば、
- 若手社員には家計管理や貯蓄の基本
- 中堅社員には資産形成やライフプランニング
- 管理職には部下のキャリア支援と関連付けた金融知識
といったように、対象者に合わせた内容を提供することで、より高い学習効果が期待できます。
実施後の効果確認とフィードバック"
金融教育プログラムを実施した後は、その効果を適切に測定し、フィードバックを行うことが重要です。目標設定時に定めたKPIの達成状況を確認したり、従業員へのアンケートやヒアリングを通じて、プログラム内容の理解度、満足度、そして実際の行動変容に繋がったかなどを評価します。
従業員からのフィードバックを収集し、プログラム内容や実施方法の改善点を見つけ出し、次回の教育に活かすことで、より効果的な金融教育体制を構築していくことができます。PDCAサイクルを回しながら継続的に改善を行うことが、金融教育の成果を最大化させる鍵となります。
従業員の声:金融教育を受けての変化
金融教育は、従業員の個人的な生活だけでなく、仕事に対する意識やキャリアに対する考え方にも良い影響を与えることがあります。実際に金融教育を受けた従業員は、どのような変化を感じているのでしょうか。
金融リテラシー向上による生活の変化
金融教育を受けた従業員からは、家計管理が楽になった、将来への漠然とした不安が軽減されたといった声が多く聞かれます。自身の収入と支出を正確に把握し、計画的にお金を管理できるようになることで、無駄遣いが減り、貯蓄や資産形成に対する意識が高まります。
また、NISAやiDeCoといった制度に関する知識を得ることで、より効率的な資産形成に取り組むことができるようになり、将来のライフイベントに向けた準備を進めやすくなったという変化も生まれています。
仕事へのモチベーションの変化

経済的な不安が軽減されることは、仕事への集中力やモチベーションの向上に繋がります。お金の心配が減ることで、業務に集中しやすくなり、パフォーマンスの向上に繋がるという従業員もいます。
また、企業が自身の経済的な安定をサポートしてくれるという安心感から、会社へのエンゲージメントや貢献意欲が高まることも期待できます。
金融教育は、従業員が安心して長く働き続けるための重要な要素となり得るのです。
今後のキャリア設計への影響
金融教育を通じて、自身のライフプランとキャリアプランを合わせて考えるきっかけを得る従業員もいます。将来必要となる資金を把握することで、現在の仕事における収入や昇進、あるいは転職といったキャリア選択について、より具体的に検討できるようになります。
また、資産形成の重要性を理解することで、FIRE(FinancialIndependence,RetireEarly:経済的自立と早期リタイア)といった新しい働き方やライフスタイルを視野に入れるなど、自身のキャリアに対する考え方が広がる可能性もあります。
まとめ
日本において金融教育が十分に浸透していない現状には、お金に関するタブー視、学校教育における課題、そして金融商品への消極的な姿勢など、複数の要因が絡み合っています。
しかし、個人のライフプランニングや資産形成、さらには企業の持続的な成長にとって、金融リテラシーの向上は不可欠です。
企業が金融教育に積極的に取り組むことは、従業員の生活安定と生産性向上、企業の社会的責任の遂行とブランド価値向上、そして離職率の低下と人材定着といった多岐にわたるメリットをもたらします。
企業が金融教育を導入する際には、従業員のニーズを把握し、目的に合わせたプログラムを継続的に提供することが重要です。
成功事例も参考にしながら、企業と従業員双方にとって有益な金融教育を進めていくことが求められています。
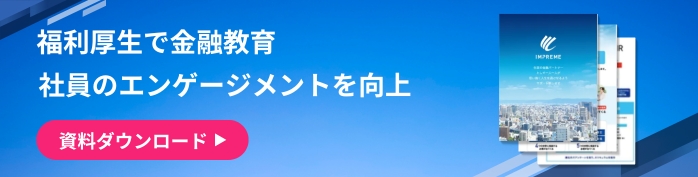

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。