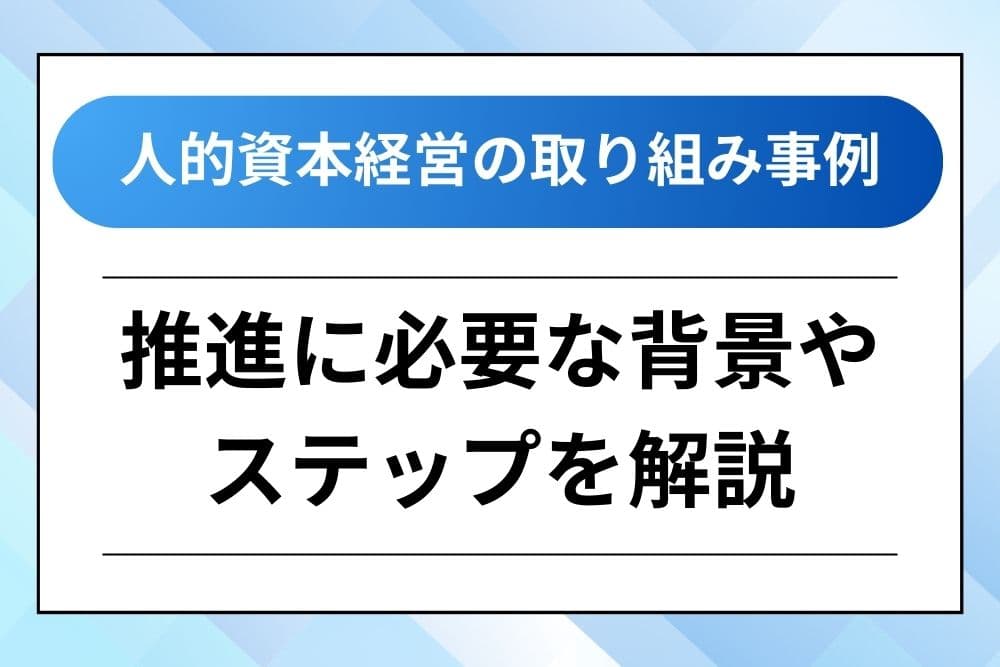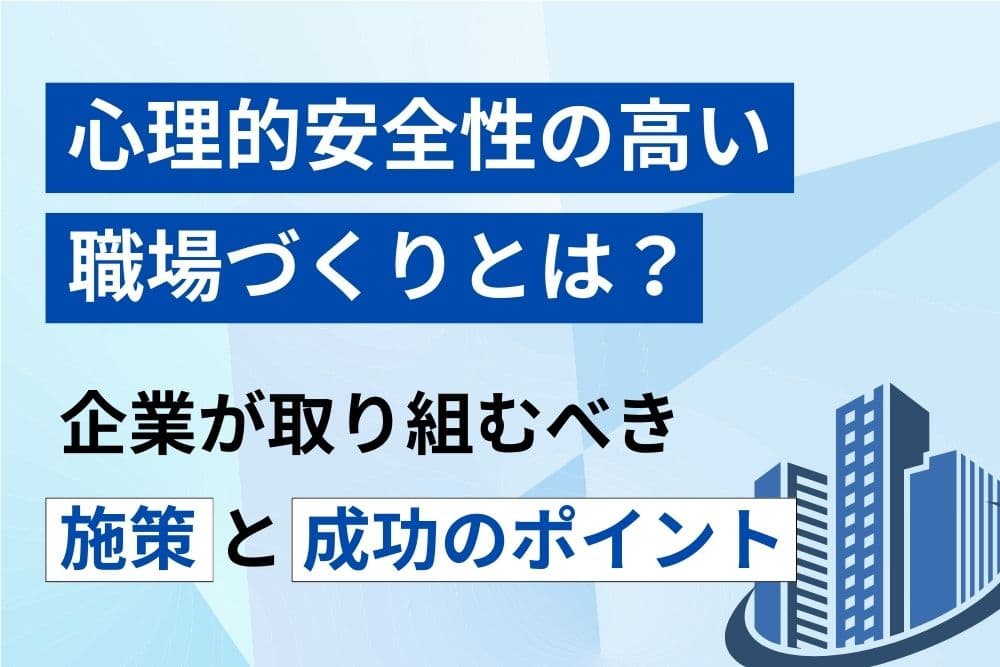お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
帰属意識とは? 会社における帰属意識の定義から高め方まで徹底解説
 詳細を見る
詳細を見る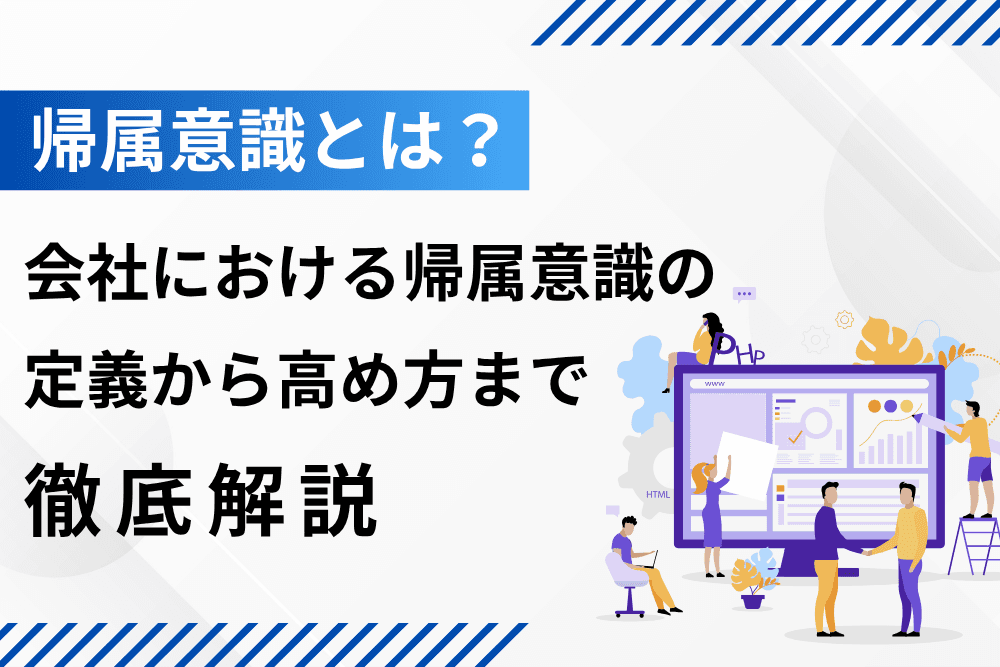
帰属意識の基本的な意味
従業員の帰属意識が高い場合の利点
帰属意識が低いとどうなるか
帰属意識を高めるための施策
帰属意識が低くなる原因と対処法
「帰属意識」という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。終身雇用制度の終焉や働き方の多様化が進む現代において、従業員の会社への帰属意識は組織の安定性や成長に欠かせない要素として再び注目されています。
この記事では、帰属意識とは何か、その基本的な意味から、会社への帰属意識を高める方法、そして帰属意識が低い場合にどのような影響があるのかを詳しく解説します。
目次
帰属意識の基本的な意味
帰属意識とは、特定の集団や組織に自分が属しているという認識や感覚を指します。これは単に物理的に所属しているだけでなく、その組織の一員であることへの愛着や一体感を含みます。
ビジネスにおける会社への帰属意識は、社員が自身の所属する企業に対して抱く「自分はその会社の一員である」という自覚や愛着、貢献したいという気持ちとして捉えられます。
帰属意識とは何か

帰属意識とは、個人がある特定の集団や組織に所属しているという意識や感覚のことです。
これは心理学の分野で用いられてきた言葉ですが、ビジネスにおいては、社員が自身が所属する企業に対して「自分はその会社の一員である」という自覚や、組織への愛着を持つことを指す場合が多く、会社への帰属意識として捉えられます。
帰属意識が高い社員は、組織の一員として貢献したいという能動的な感覚を持ち、組織や方針への興味関心が高いという特徴が見られます。
エンゲージメントとの相違点
帰属意識と混同されやすい言葉に「エンゲージメント」がありますが、これらは異なる概念です。帰属意識がある集団への愛着や一体感を指すのに対し、エンゲージメントは従業員が会社や組織、業務に対して抱くポジティブな結びつきや貢献意欲を意味します。
帰属意識は社員から企業への一方通行の意識であるのに対し、エンゲージメントは企業と社員双方の肯定的なつながりの強さを示す双方向性の概念と言えるでしょう。
従業員エンゲージメントが高い状態は、企業で働くことに誇りを感じ、企業理念やビジョンに強く共感している状態を指し、エンゲージメントを高めることが帰属意識の向上につながると考えられています。
従業員の帰属意識が高い場合の利点
従業員の会社への帰属意識が高いことは、組織にとって様々な利点をもたらします。社員が組織に対して愛着や貢献意欲を持つことで、組織全体の活性化や業績向上に繋がることが期待できます。
離職率の抑制につながる
企業への帰属意識が高い従業員は、「この企業に長く勤めたい」という気持ちを強く持つ傾向があります。そのため、離職を考える可能性が低くなり、結果として離職率の低下に繋がります。
人材不足が課題となる現代において、従業員の定着率向上は企業の安定的な運営に不可欠であり、長期的な人材確保に繋がるでしょう。
従業員の意欲が向上する

帰属意識が高い従業員は、自分が組織に必要とされていると感じやすく、仕事への意欲が高い傾向にあります。「この企業を支えたい」「チームで連携して業績を上げたい」といったように、仕事へ熱意を持って取り組むようになり、モチベーションの向上に繋がります。
モチベーションが高まることで、自発的な行動や仕事への積極性が増すことが期待できます。
チームワーク・風通しのよい職場環境が築かれる
帰属意識が高い従業員は、自分が組織の一員であるという意識を強く持つため、部署内でのチームワーク向上にも繋がります。従業員同士で適度なコミュニケーションをとることは帰属意識の向上に影響を与え、お互いに協力して目標を達成しようとする気持ちが高まります。
コミュニケーションが活性化することで、風通しの良い職場環境の構築に繋がるでしょう。
生産性や業務効率の向上
帰属意識が高まり、仕事への意欲が増すと、従業員は主体的に業務に取り組むようになります。「やらされている感」ではなく、「組織の一員として成長したい」「市場価値の高い仕事をしたい」という気持ちで働くようになり、目標達成意欲も高まります。
これにより、個々の生産性や業務効率の向上に繋がり、組織全体の生産性向上に好影響を与えます。
帰属意識が低いとどうなるか
従業員の会社への帰属意識が低い状態は、組織にとって様々な問題を引き起こす可能性があります。モチベーションやエンゲージメントの低下、そしてそれに伴う離職リスクの増加などが挙げられます。
離職リスク、エンゲージメント低下の負の連鎖
帰属意識が低い、あるいは持てない従業員は、企業に対する愛着が薄れ、「この企業で働き続ける理由がない」と感じやすくなります。これにより、離職率の増加に繋がる可能性が高まります。
また、帰属意識の低さはエンゲージメントの低下にも繋がり、仕事への貢献意欲や誇りを持てなくなるという負の連鎖を生み出すことがあります。
離職者が増えると、既存の従業員への業務負担が増加し、さらなる離職を招く悪循環に陥る可能性も考えられます。
低帰属状態が引き起こす職場の問題行動
帰属意識が低い従業員は、仕事に対するモチベーションを維持することが難しくなり、仕事に対して受け身になりがちです。組織の一員であるという意識が軽薄になるため、自発的な行動が減少し、業務効率や生産性の低下を招く可能性があります。
また、自分の仕事や組織の目標への関心が薄れ、どのように貢献できるかを考えずに仕事をしてしまう場合もあります。組織への愛着のなさから、組織の問題や課題を他人事として捉えてしまう可能性も高まります。
若手社員に多い傾向とその理由
近年、終身雇用の崩壊や働き方の多様化により、若手社員を中心に会社への帰属意識が希薄になる傾向が見られます。これは、仕事に対する価値観の変化や、インターネットの普及により他社の情報に触れる機会が増えたことなども影響しています。
企業に対する帰属意識よりも、自身のキャリアやライフスタイルを重視する若手社員が増えていることも、この傾向に拍車をかけていると言えるでしょう。
帰属意識を高めるための施策
従業員の会社への帰属意識を高めるためには、企業側が意識的に様々な取り組みを行うことが重要です。コミュニケーションの活性化や企業理念の浸透、良好な人間関係の構築などが効果的な施策として挙げられます。
従業員同士や上司・部下間のコミュニケーションを活性化させることは、帰属意識を高める上で非常に効果的です。気軽に話せる場を設けたり、部署を越えた交流の機会を創出したりすることで、従業員間の信頼関係や仲間意識が醸成されます。
社内イベントやシャッフルランチなども、業務外でのコミュニケーションを促進し、組織への愛着を深めることに繋がるでしょう。
ビジョンや理念の浸透
企業のビジョンや理念を従業員に明確に伝え、共感を促すことは、帰属意識を高める上で不可欠です。企業が目指す方向性や社会における存在意義を理解することで、従業員は自身の業務がどのように企業に貢献しているのかを認識しやすくなります。
企業理念やバリューを浸透させるためのインナーブランディングは、従業員の愛着や一体感を醸成し、帰属意識の向上に繋がります。
上司と部下の信頼関係を構築する
上司と部下の間に良好な信頼関係があることは、チーム全体の帰属意識を高める上で重要です。上司が部下の意見に耳を傾け、適切なフィードバックを行うことで、部下は組織の一員として認められていると感じ、安心感や信頼感を抱くようになります。
定期的な1on1ミーティングなどを通じて、個々の従業員の悩みやキャリアについて話し合う機会を設けることも有効です。
組織文化や風土を整備する
従業員が居心地良く働ける組織文化や風土を整備することは、帰属意識の向上に繋がります。従業員同士が互いを尊重し、協力し合う雰囲気を醸成することで、安心感を持って業務に取り組めるようになります。
チャレンジを賞賛する文化や、失敗を恐れずに意見を言える環境を作ることも重要です。
評価制度・処遇に公平性をもたせる
従業員の貢献が適切に評価され、公平な処遇がなされることは、帰属意識に大きく影響します。評価基準の明確化や、業務内容に見合った報酬体系の整備は、従業員のモチベーションと信頼感を高めます。
待遇への不満は帰属意識の低下に直結するため、透明性のある評価制度と、従業員の声を反映した待遇の整備が求められます。
社内イベント・オフサイトミーティングの効果
社内イベントやオフサイトミーティングは、普段業務で関わりの少ない従業員同士が交流する貴重な機会となります。部署や役職を越えたコミュニケーションを通じて、相互理解を深め、組織全体の一体感を醸成することができます。
これにより、会社への愛着や帰属意識を高める効果が期待できます。
帰属意識が低くなる原因と対処法
従業員の帰属意識が低くなる原因は様々ですが、それらを理解し、適切な対処法を講じることで、帰属意識を高めることが可能です。
コミュニケーション不足や評価への不満などが主な要因として挙げられます。
管理職の意識不足
管理職が従業員の帰属意識の重要性を理解していなかったり、部下とのコミュニケーションを怠ったりすることは、帰属意識が低くなる原因の一つとなります。管理職は、部下が組織の一員として安心して働ける環境を作る責任があり、個別に関心を持ち、サポートする意識を持つ必要があります。
企業は管理職向けの研修などを通じて、部下の帰属意識を高めるための意識付けを行うことが重要です。
評価・報酬への不満

従業員が自身の働きや貢献が正当に評価されていないと感じたり、報酬に不満を持ったりする場合、会社への帰属意識は低下しやすくなります。
透明性のある評価制度を整備し、従業員の成果や努力を適切に評価に反映させる必要があります。
また、給与や福利厚生といった待遇面についても、従業員が納得できる水準であるかを見直すことが、帰属意識を高める上で重要です。
個人主義的な社風
過度に個人主義的な社風や、従業員同士の関わりが希薄な職場環境は、帰属意識が育まれにくい要因となります。
従業員が孤立感を感じたり、自分の居場所がないと感じたりする場合、組織への愛着は薄れてしまいます。
チームワークを重視する文化を醸成し、従業員同士が協力し合い、支え合えるような環境を整備することが、帰属意識を高めるために必要です。
キャリアパスの不透明さ
自身の会社でのキャリアパスが見えにくいと感じる場合、従業員の帰属意識は低下する可能性があります。自分がその会社でどのように成長し、貢献していけるのかが不明確であると、将来への不安を感じ、他の機会を探すことに繋がりかねません。
企業は明確な評価制度やキャリアアップの機会を示すことで、従業員が自身の将来を会社の中で描けるようにサポートする必要があります。
社員の声を拾いきれていない体制
従業員が会社に対して抱いている意見や不満が経営層や管理職に届かない体制では、従業員は「自分の声は無視されている」と感じ、帰属意識を失ってしまいます。定期的な従業員サーベイや1on1などを通じて、従業員の生の声を聞き、それらを改善に繋げる姿勢を示すことが重要です。
従業員の意見が尊重され、組織づくりに参加できていると感じられる環境は、帰属意識を高めることに繋がります。
中小企業・スタートアップがとるべき戦略
リソースが限られている中小企業やスタートアップでも、従業員の帰属意識を高めるための効果的な戦略は存在します。大企業とは異なる特性を活かし、従業員との距離感を縮める取り組みが重要となります。
限られたリソースで帰属意識を高めるには
中小企業やスタートアップは、大企業に比べて利用できるリソースが限られていることが多いですが、工夫次第で帰属意識を高めることは十分に可能です。
高額な研修プログラムや大規模な社内イベントを実施するのが難しい場合でも、日々のコミュニケーションの質を高めたり、従業員の意見を丁寧に拾い上げたりするなどの取り組みによって、従業員の会社への愛着や一体感を醸成することができます。
限られたリソースを効果的に活用するためには、従業員にとって何が重要かを理解し、優先順位をつけて施策を実行することが大切です。
経営層と従業員の距離感を活かす
中小企業やスタートアップでは、経営層と従業員の物理的・心理的な距離が近いことが多いという特徴があります。この距離感の近さを活かし、経営層が積極的に従業員とコミュニケーションを取ることで、一体感を醸成しやすくなります。
経営理念やビジョンを直接伝える機会を設けたり、従業員からの意見や提案を丁寧に聞いたりすることで、従業員は自身が会社の重要な一員であると感じ、帰属意識を高めることに繋がるでしょう。
オンボーディングと日常の声かけの重要性
特に中小企業やスタートアップにおいて、新入社員のオンボーディングは帰属意識を早期に育む上で非常に重要です。丁寧なオンボーディングプログラムを通じて、会社の文化や働く仲間について理解を深めてもらうことで、孤立感を軽減し、組織への馴染みを促進します。
また、日々の業務の中での何気ない声かけや、感謝の気持ちを伝えることも、従業員の安心感や居場所意識を高めることに繋がり、帰属意識の向上に貢献します。
帰属意識を測定・可視化する方法
従業員の帰属意識の状態を把握し、具体的な改善策に繋げるためには、定期的な測定と可視化が有効です。サーベイやアンケートの実施、そして適切な指標の設定が重要となります。
サーベイ・アンケートの設計方法
従業員の帰属意識を測定する最も一般的な方法の一つが、サーベイやアンケートの実施です。効果的なサーベイを設計するためには、帰属意識に関連する項目を網羅的に含める必要があります。
例えば、会社への愛着、組織の一員であることへの自覚、同僚や上司との関係性、会社のビジョンへの共感などを問う質問を含めると良いでしょう。無記名で実施することで、従業員が正直な意見を伝えやすい環境を作ることが重要です。
指標例:ロイヤリティ・貢献意欲など
帰属意識を測定する際の具体的な指標としては、組織へのロイヤリティ(忠誠心)、組織に貢献したいという意欲、組織の一員として留まりたいという願望などが挙げられます。これらの指標を定量的に測定することで、従業員の帰属意識の度合いを把握することができます。
また、これらの指標は従業員エンゲージメントの要素とも関連しており、エンゲージメントサーベイの結果と合わせて分析することで、より多角的に従業員の状態を理解することに繋がります。
可視化ツール・サービスの紹介
サーベイやアンケートで収集したデータを効果的に分析し、可視化するためには、専用のツールやサービスの活用が有効です。これらのツールを利用することで、組織全体の帰属意識の傾向や、部署・チームごとの特徴などを把握しやすくなります。
結果をグラフなどで視覚的に表現することで、課題となっている領域を特定し、具体的な改善策の検討に役立てることができます。エンゲージメントサーベイツールの中には、帰属意識やエンゲージメントの状態を可視化し、分析をサポートする機能を持つものもあります。

まとめ
企業における帰属意識は、従業員が組織の一員であるという自覚や愛着であり、離職率の抑制や従業員のモチベーション向上、生産性の向上など、組織の成長にとって非常に重要な要素です。
終身雇用の崩壊や働き方の多様化により帰属意識が低下しやすい現代において、企業が意識的に帰属意識を高めるための施策に取り組むことは不可欠です。
コミュニケーションの活性化、企業理念の浸透、良好な人間関係の構築、公平な評価制度の整備など、様々な側面からのアプローチが効果的です。
定期的な測定や可視化を通じて、自社の帰属意識の状態を把握し、従業員が「この会社に居続けたい」「貢献したい」と思える組織づくりを進めていくことが、持続的な企業成長に繋がるでしょう。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。