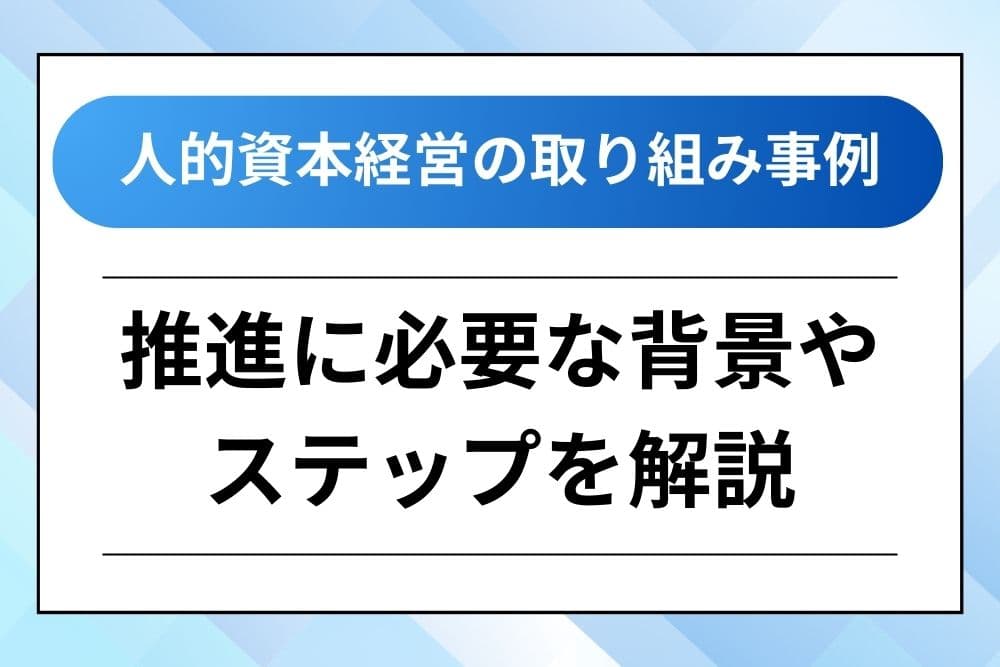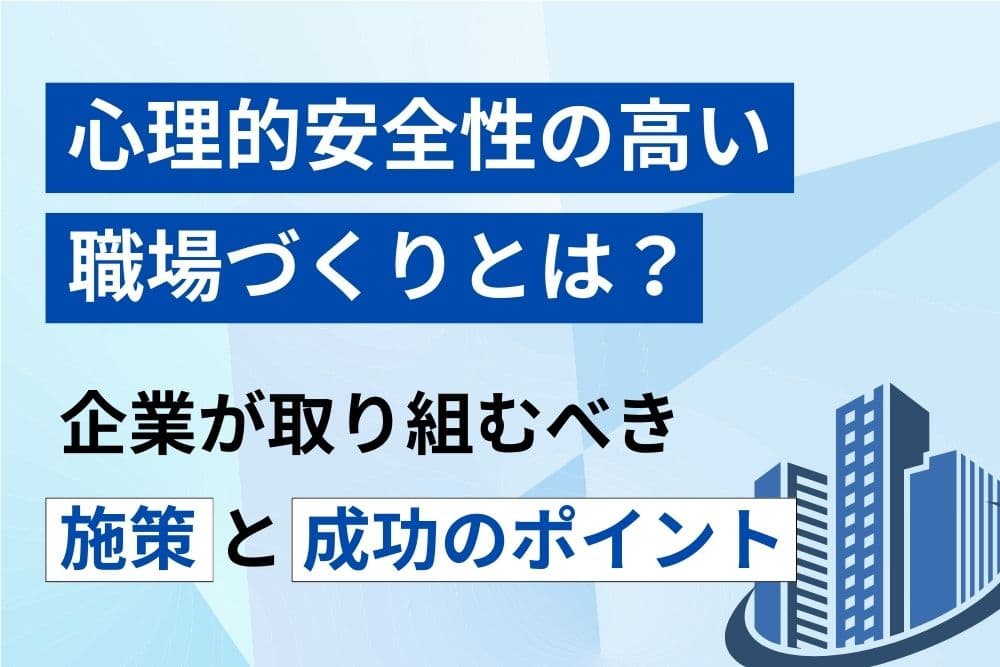お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
モチベーションとエンゲージメントの違いと高め方
 詳細を見る
詳細を見る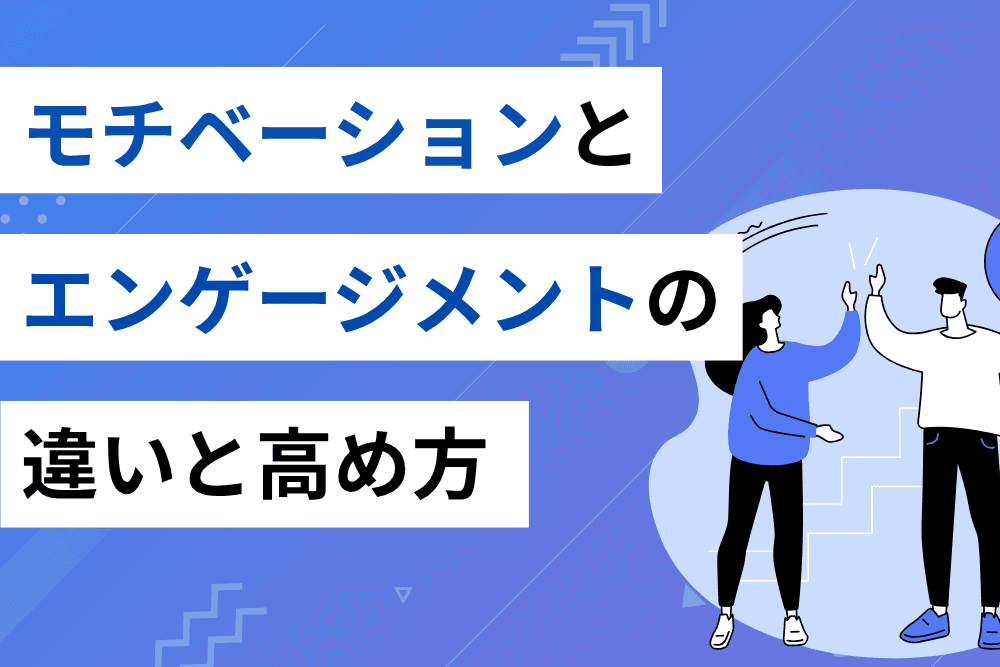
モチベーションとは
モチベーションとエンゲージメントの違い
モチベーションを高めるための施策
エンゲージメントを高めるための施策
中小企業やスタートアップに適した方法
組織の成長に不可欠な要素として、「モチベーションとエンゲージメント」が挙げられます。
しかし、これら二つの言葉の「違い」を明確に理解できていない方もいるかもしれません。
モチベーションは「仕事に対する従業員のやる気・意欲」といった個人の内面的な動機に焦点を当てたものであり、一方のエンゲージメントは「組織と従業員との双方向のつながり」や、組織の目標達成に向けた貢献意欲を指します。
本記事では、エンゲージメントとモチベーションの違いを掘り下げ、それぞれの重要性や高めるための具体的な施策、さらには測定方法について詳しく解説します。
目次
モチベーションとは
モチベーションとは、特定の目的や目標に向かって行動を起こし、それを維持するための内面的なエネルギーや意欲を指します。個人の「やる気」や「動機づけ」と言い換えることもでき、行動の方向性を定め、その行動を持続させる働きがあります。
モチベーションの高さは、従業員が自発的に仕事に取り組み、困難な課題にも積極的に挑戦する姿勢に繋がります。エンゲージメントとモチベーションの違いを理解する上で、モチベーションは個人の内面に根ざしたものであるという点が重要となります。
モチベーションの定義と種類

モチベーションは、目標達成に向けて行動を起こす際の原動力であり、「やる気」や「意欲」、「動機づけ」といった言葉で表されます。これは行動の方向性を定め、それを継続させる力でもあります。
モチベーションが高い従業員は、自発的に行動し、目標に向かって粘り強く取り組み続ける傾向にあります。個人の成長やスキルアップへの意識も高く、難しい業務にも積極的に挑戦し、結果として組織への貢献に繋がることが期待できます。
ワークエンゲージメントという言葉もありますが、これは仕事への没頭や熱意といった側面を指し、エンゲージメントとモチベーションの違いを考える上で、モチベーションがより広範な「やる気」全般を指すのに対し、ワークエンゲージメントは仕事に特化した意欲に焦点が当たると理解できます。
内発的/外発的モチベーションの違い
モチベーションは、その源泉によって内発的モチベーションと外発的モチベーションの二種類に分けられます。内発的モチベーションは、自身の興味や関心、やりがいといった内面的な要因から生まれる「やる気」です。
仕事そのものが面白い、新しい知識を得ることが楽しい、といった感情がこれにあたります。一方、外発的モチベーションは、報酬や評価、罰則の回避といった外部からの刺激によって引き起こされるモチベーションです。
給与の上昇を目指したり、昇進を目標にしたりすることが外発的モチベーションの例です。これら二つのモチベーションは、個人の行動を促す上で異なる影響力を持っています。内発的モチベーションは、より持続的で主体的な行動に繋がりやすいと考えられています。
モチベーションが低下するとどうなるのか
モチベーションが低下すると、仕事への意欲や関心が薄れ、「やらされ感」を持って業務に取り組むようになります。自発的な行動が減少し、必要最低限のことしか行わなくなる傾向が見られます。これは業務の効率や質の低下に繋がり、成果が出にくくなるという悪循環を生む可能性があります。
モチベーションの低下は、個人の成長意欲の減退にも繋がり、新しい業務やスキルの習得に消極的になることも考えられます。また、モチベーションが低い状態は、職場の雰囲気を悪化させたり、チーム内の協力体制を乱したりするなど、周囲にも悪影響を及ぼしかねません。
生産性の低下は組織全体の業績悪化にも繋がり、従業員の離職リスクを高める要因ともなります。エンゲージメントとモチベーションとの関係においても、モチベーションの低下はエンゲージメントの低下に繋がりやすく、組織と従業員の関係性が希薄になる可能性があります。
エンゲージメントとは
エンゲージメントは、従業員が組織に対して持つ愛着心や貢献意欲、そして組織の目標達成に向けた自発的な関与の度合いを指します。これは単なる従業員満足度とは異なり、組織と従業員との間の「深いつながり」や「互いに貢献し合う関係性」を意味します。
エンゲージメントとモチベーションの違いを理解する上で、エンゲージメントは組織との関係性に焦点が当てられている点が重要です。高いエンゲージメントは、従業員が組織の一員としての自覚を持ち、組織の成長を自身の課題と捉え、積極的に業務に取り組む姿勢に繋がります。
関連記事:従業員エンゲージメントとは
エンゲージメントの定義と構成要素
エンゲージメントは、企業と従業員が互いに信頼し合い、組織の成功に向けて貢献し合う関係性を指します。これは単に「従業員満足度」が高いという状態とは異なります。
従業員満足度は、給与や福利厚生、労働環境といった企業から与えられるものに対する満足度を測る指標であり、満足度が高くても必ずしも仕事への情熱や貢献意欲に繋がるわけではありません。
エンゲージメントは、従業員が企業の理念やビジョンに共感し、組織の一員として積極的に関与したいという主体的な意思を含んでいます。エンゲージメントを構成する主な要素としては、
- 「理解度」
- 「共感度」
- 「行動意欲」
が挙げられます。
従業員が企業の目標や価値観を理解し、それに共感し、そして組織の成功のために自発的に行動しようとする意欲を持っている状態が高いエンゲージメントと言えるでしょう。
エンゲージメントと従業員満足度との違いを理解することは、組織の活性化に向けた適切な施策を検討する上で重要です。
高エンゲージメントの状態とは

高エンゲージメントの状態とは、従業員が単に職務に満足しているだけでなく、組織の目標や価値観に深く共感し、自身の業務を通じて組織に貢献したいという強い意欲を持っている状態を指します。
この状態にある従業員は、与えられた業務をこなすだけでなく、自発的に新しい課題に取り組み、困難な状況でも粘り強く問題解決にあたります。組織の一員としての自覚が高く、同僚との連携も円滑に行い、チーム全体の成果向上にも積極的に貢献します。
ロイヤリティ(忠誠心)と似ている側面もありますが、高エンゲージメントは単なる企業への一方的な忠誠ではなく、組織との双方向の関係性の中で生まれるものです。
企業が従業員の成長や幸福を支援し、従業員がその組織に貢献することでやりがいや成長を実感できる、そのような相互作用が強い組織との違いを生み出し、高いエンゲージメントを育みます。
結果として、生産性や業績の向上、離職率の低下といった組織にとって好ましい結果に繋がることが期待できます。
モチベーションとエンゲージメントの違い
モチベーションとエンゲージメントは、企業の成長に不可欠な要素でありながら、それぞれ異なる側面に焦点を当てています。モチベーションが個人の内面的な「やる気」や「意欲」を指すのに対し、エンゲージメントは組織と従業員との間の「心理的な結びつき」や「貢献意欲」を指します。
エンゲージメントとモチベーションは相互に関連し合うものの、その違いを明確に理解することは、効果的な人材戦略を立てる上で重要です。
モチベーションは「個人のやる気」、エンゲージメントは「組織の関係性や心理的結びつき」
モチベーションとエンゲージメントは、どちらも従業員の働く意欲に関わる概念ですが、その焦点と性質において違いがあります。モチベーションは、個人的な欲求や目標達成に向けた内面的な動機、つまり「個人のやる気」に焦点を当てています。
昇給や昇進といった外的な報酬や、自己成長、仕事への興味といった内的な要因によって影響を受けます。
一方、エンゲージメントは、従業員と組織との間の「関係性」や「心理的な結びつき」に重点を置いています。従業員が企業のビジョンや文化に共感し、組織の一員として貢献したいという意識や、仕事への没頭度合いを含みます。
エンゲージメントとモチベーションは、どちらも従業員のパフォーマンスや定着率に影響を与えますが、モチベーションが短期的な行動を促す側面が強いのに対し、エンゲージメントはより長期的で持続的な組織への貢献に繋がると言えます。
両者の相関関係と相互作用
モチベーションとエンゲージメントは、異なる概念ではありますが、互いに影響し合う密接な関係にあります。従業員のモチベーションが高まると、仕事に対して意欲的に取り組み、目標達成に向けて熱心に努力します。
この積極的な姿勢は、自身の成長や成果に繋がり、それが組織への貢献実感や一体感を生み出し、結果としてエンゲージメントの向上に繋がることがあります。
逆に、エンゲージメントが高い社員は、組織の目標や価値観に共感し、組織の一員としての自覚が強いため、自身の業務に対する責任感や主体性が増し、それがモチベーションの向上に繋がることが期待できます。
つまり、モチベーションとエンゲージメントは一方が他方を高める好循環を生み出す可能性があるのです。しかし、必ずしも常に相乗的に向上するわけではありません。
例えば、個人のモチベーションが高くても、組織のビジョンへの共感や貢献できる環境がなければ、エンゲージメントは高まりにくいでしょう。
この相関関係と相互作用を理解し、両方をバランス良く高める施策を講じることが、社員の活性化と組織力強化には不可欠です。
活用場面の違い
モチベーションとエンゲージメントは、それぞれ焦点を当てる対象が異なるため、企業が活用する場面も異なります。モチベーションは、個人の短期的なパフォーマンス向上や特定の業務への取り組みを促したい場面で活用されます。
例えば、営業目標達成に向けたインセンティブ制度や、特定のプロジェクトにおける個人の「やる気」を引き出すための声かけなどがこれにあたります。個人の内面的な動機に働きかけることで、目の前の業務に対する集中力や行動力を高めることを目指します。
一方、エンゲージメントは、より長期的で組織全体に関わる目標に対して活用されます。
組織文化の醸成、離職率の低下、チームワークの強化、そして社員の定着率向上といった、組織と従業員の継続的な関係性を築き、強化したい場面で重要な指標となります。
会社のビジョン浸透施策や、従業員の意見を吸い上げるための仕組み作りなどは、エンゲージメントを高めるための取り組みと言えます。
つまり、モチベーションは個人のエネルギーを特定の行動に結びつける際に、エンゲージメントは組織全体の活性化や持続的な成長を目指す際に、それぞれ効果的に活用されます。
モチベーションを高めるための施策
従業員のモチベーションは、個人のパフォーマンスや組織全体の生産性に直結する重要な要素です。モチベーションとエンゲージメントを同時に高めていくことは理想的ですが、まずは個人の「やる気」に焦点を当てた施策も効果的です。
具体的な施策としては、成果に基づいた報酬制度の導入、個々のキャリアパスを明確にする支援、そして上司からの適切なフィードバックなどが挙げられます。
成果連動型の報酬制度
成果連動型の報酬制度は、従業員の「やる気」を直接的に刺激し、特定の目標達成に向けた行動を促進する効果的な施策の一つです。
個人の業績やチーム、あるいは組織全体の成果に応じて報酬やインセンティブを連動させることで、従業員は自身の努力が具体的に報われることを認識し、さらなる高みを目指そうという意欲を高めます。
この制度は、特に目標が明確で個人の貢献度が測りやすい業務において、仕事への集中力を高め、生産性の向上に繋がりやすいと考えられます。
ただし、成果のみを過度に重視する制度は、従業員間の過当競争を引き起こしたり、短期的な成果追求に偏り、長期的な視点やチームワークを損なう可能性もあるため、導入には慎重な検討と、他のモチベーション施策とのバランスが重要です。
パーパス・キャリア設計の明確化
社員一人ひとりが自身の仕事の目的や意義(パーパス)を理解し、組織内での長期的なキャリアパスを描けるように支援することは、内発的なモチベーションを高める上で非常に効果的です。
会社が目指すビジョンや社会的な存在意義を明確に伝え、それが個々の業務とどのように繋がっているのかを示すことで、社員は自身の仕事が単なる作業ではなく、より大きな目標達成に貢献していることを実感できます。
また、定期的な1on1ミーティングやキャリア相談などを通じて、個人のスキルや志向に合わせた成長機会を提供したり、将来のキャリアステップを具体的に示すことで、社員は自身の成長や将来に対する希望を持つことができます。
これにより、自身のキャリア形成に向けて主体的に学び、積極的に業務に取り組む「やる気」を引き出すことが期待できます。自身の成長が組織の成長に繋がるという認識は、エンゲージメントの向上にも良い影響を与えます。
上司からのポジティブフィードバック
上司から部下へのポジティブフィードバックは、社員のモチベーションを高める上で非常に重要な要素です。日々の業務における努力や成果、良い行動に対して具体的に承認し、褒めることで、社員は自身の貢献が認められていると感じ、自己肯定感が高まります。
これにより、さらなる「やる気」を引き出し、積極的に業務に取り組む姿勢を強化できます。
ポジティブフィードバックは、単に結果だけでなく、そこに至るまでのプロセスや、チームへの良い影響なども含めて伝えることが効果的です。
また、フィードバックはタイムリーに行うことが重要であり、良い行動が見られたら間を置かずに伝えることで、より行動の定着に繋がりやすくなります。
定期的な1on1ミーティングの場で、目標達成に向けた進捗と共にポジティブな側面をしっかりと伝えることも有効な方法です。ポジティブフィードバックは、社員の自信を育み、前向きな気持ちで仕事に取り組むための強力な後押しとなります。
エンゲージメントを高めるための施策
エンゲージメントは、従業員と組織の間の深いつながりを育み、組織への貢献意欲を高めるために不可欠です。エンゲージメントとモチベーションは相互に関連しますが、エンゲージメントの向上には組織文化や環境に焦点を当てた施策が求められます。
具体的には、従業員が安心して働ける福利厚生の整備、企業の理念や価値観を共有・浸透させる取り組み、そして双方向のコミュニケーションを促進する仕組み作りなどが効果的です。
福利厚生の整備
福利厚生の充実は、社員が安心して働くための基盤を築き、企業への信頼感や帰属意識を高める上で重要な施策です。
経済的な支援や健康面への配慮、育児や介護との両立支援など、社員のライフステージや多様なニーズに合わせた福利厚生を整備することで、「会社が自分たちのことを大切にしてくれている」という実感に繋がり、エンゲージメントの向上に貢献します。
例えば、住宅手当や通勤手当といった基本的なものから、カフェテリアプランのように社員が自身のニーズに合わせて自由に選択できる制度、さらには病気や怪我をした際のサポート体制、メンタルヘルスケアの充実なども含まれます。
これらの福利厚生が整っていることは、社員の満足度を高めるだけでなく、企業への愛着や「この会社で長く働きたい」という気持ちを育むことに繋がります。結果として、離職率の低下にも効果が期待できます。
ビジョン・バリューの定着施策
企業のビジョン※1・バリュー※2を明確にし、それを社員一人ひとりに深く理解・共感してもらうことは、エンゲージメントを高めるための核となる施策です。
企業が何を目指し、どのような価値観を大切にしているのかを共有することで、社員は自身の業務が組織全体の目標にどのように繋がっているのかを理解し、働く意義を見出しやすくなります。
- 1.ビジョン:ミッションを土台に描く中長期的な理想像で企業が「将来どうありたいか」を示す
- 2.バリュー:ミッションの実現とビジョンの達成に向け、社員が日々の行動で体現すべき価値観・判断基準
ビジョン・バリューを浸透させるためには、単に社内報やポスターで掲示するだけでなく、経営層が繰り返しメッセージを発信したり、日々の業務における判断基準として活用したり、評価制度に組み込んだりするなど、様々な機会を通じて具体的に示すことが重要です。
また、社員がビジョン・バリューについて話し合い、自分たちの言葉で理解を深めるワークショップなどを実施することも効果的です。
MVV(ミッション※3・ビジョン・バリュー)が社員に深く根付くことで、組織に対する共感や愛着が生まれ、主体的に組織に貢献したいというエンゲージメントが高まります。
- 3.ミッション:企業が社会に存在する理由、使命を端的に示したも宣言
社内SNS・1on1ミーティングの活用
社内SNSや1on1ミーティングは、従業員間のコミュニケーションを活性化させ、組織内の人間関係を良好に保つ上で有効なツールであり、エンゲージメント向上に貢献します。
社内SNSは、部署や役職を超えたフランクな情報共有や、個人の興味・関心に基づいたコミュニティ形成を促進し、従業員同士の繋がりや一体感を醸成するのに役立ちます。
業務に関する情報だけでなく、個人的な出来事や趣味などを共有することで、お互いをより深く理解し、親近感を持つことができます。
一方、1on1ミーティングは、上司と部下が定期的に一対一で対話する機会であり、業務の進捗確認だけでなく、キャリアに関する相談、悩みや懸念事項の共有、そして個人的な価値観の理解など、多岐にわたる内容を話すことができます。
これにより、部下は「自分は会社や上司から気にかけてもらえている」と感じ、安心感や信頼感が生まれ、エンゲージメントが高まります。また、上司は部下の状況を把握し、個別のサポートを行うことで、部下の成長を支援し、より強い信頼関係を築くことができます。
これらのツールを効果的に活用することで、組織内の風通しが良くなり、従業員が心理的な安全性を感じながら働くことができる環境が整備され、エンゲージメントの向上に繋がります。
柔軟な働き方の導入(リモート、フレックス等)
リモートワークやフレックスタイム制度といった柔軟な働き方の導入は、従業員のワークライフバランスを向上させ、企業への満足度とエンゲージメントを高める有効な施策です。
従業員は自身の都合に合わせて働く場所や時間を選択できるようになるため、通勤時間の削減や育児・介護との両立がしやすくなり、仕事とプライベートの調和を図りやすくなります。
これにより、心身の負担が軽減され、仕事に対する満足度が高まります。また、柔軟な働き方は、従業員が自身の裁量で業務を進める機会を増やし、自律性や主体性を育むことにも繋がります。
企業側は、従業員の多様な働き方を支援することで、「従業員のことを大切にしている」というメッセージを伝えられ、従業員からの信頼感や愛着を高めることができます。
ただし、柔軟な働き方を導入する際には、情報共有の方法やコミュニケーションの頻度、評価制度の見直しなど、いくつかの課題も発生するため、それらに対する適切な対策を講じることが重要です。
適切な制度設計と運用により、柔軟な働き方は従業員のエンゲージメントを高め、生産性の向上にも寄与することが期待できます。
中小企業やスタートアップに適した方法
中小企業やスタートアップでは、大企業のような潤沢なリソースがない場合でも、従業員のモチベーションとエンゲージメントを高めるための効果的なアプローチが存在します。組織規模が小さいからこそ可能な、きめ細やかな対応や、経営層との距離の近さを活かした施策が有効となります。
限られたリソースの中でも最大限の効果を引き出すための、実践的な方法を検討することが重要です。
手間をかけずにできる個別フォロー
中小企業やスタートアップでは、組織の規模が比較的小さいため、従業員一人ひとりに対するきめ細やかな個別フォローを行いやすいという利点があります。
大規模な研修制度などを導入するのが難しくても、日々の業務の中で意識的に従業員とコミュニケーションを取り、個別の状況を把握することができます。
例えば、ランチタイムに気軽に話を聞いたり、業務の合間に「困っていることはない?」と声をかけたりするだけでも、従業員は「自分は見守られている」「気にかけてもらえている」と感じ、安心感を得られます。
また、個人の強みや興味関心を把握し、それに合わせた業務を任せたり、成長の機会を提供したりすることで、仕事へのやりがいやモチベーションを高めることができます。
定期的な1on1ミーティングを導入する際も、テンプレートに沿った形式的なものではなく、従業員の個性やその時々の状況に合わせた柔軟な対話を心がけることが重要です。
手間をかけすぎず、日常の延長線上で個別フォローを行うことが、中小企業やスタートアップにおいては、従業員のエンゲージメントとモチベーション向上に繋がりやすい方法と言えます。
経営者との距離感を活かすカルチャー形成
中小企業やスタートアップでは、経営者と社員の物理的・心理的な距離が近いという特性を活かすことで、独自の強いカルチャーを形成し、社員のエンゲージメントを高めることができます。
経営者自身が企業のビジョンやバリューを日頃から積極的に発信し、社員と直接対話する機会を設けることで、経営者の想いや企業の方向性が社員にダイレクトに伝わります。これにより、社員は組織の一員としての当事者意識を持ちやすくなり、企業に対する共感や愛着が深まります。
例えば、定期的な全社ミーティングで経営者が会社の現状や今後の展望を共有したり、少人数の座談会形式で社員からの意見や質問に答えたりすることが有効です。
また、経営者が日頃から社員一人ひとりの名前を覚えて話しかけたり、個人的な悩みにも耳を傾けたりすることで、社員は「自分は大切な存在として認識されている」と感じ、組織への強い帰属意識を持つようになります。
このような経営者と社員の距離の近さを活かしたオープンなコミュニケーションと、それを基盤としたカルチャー形成は、社員のエンゲージメントを自然な形で高める強力な手段となります。
リーダーシップよりも「共創」の姿勢を重要視する

中小企業やスタートアップにおいては、伝統的な「リーダーシップ」のあり方だけでなく、「共創」の姿勢を重要視することが、従業員のワークに対する主体性やエンゲージメントを高める上で有効です。
「共創」とは、組織内の多様なメンバーがそれぞれの知識やスキルを持ち寄り、対話を通じて共に新しい価値や解決策を生み出していくプロセスを指します。
経営者やマネージャーが一方的に指示を出すのではなく、従業員の意見やアイデアを積極的に引き出し、意思決定のプロセスに巻き込むことで、従業員は「自分たちの意見が尊重されている」「組織づくりに貢献できている」という実感を得られます。
これにより、やらされ感ではなく、自らの意思でワークに取り組む主体性が育まれ、仕事へのオーナーシップを持つようになります。
特に変化の激しい現代においては、少数のリーダーだけでは対応しきれない複雑な課題も多いため、組織全体で知恵を出し合い、柔軟に対応していく「共創」のスタイルが求められます。
この「共創」の姿勢は、従業員間の相互理解や協力関係も促進し、チーム全体のワークエンゲージメント向上にも繋がります。
リーダーは、全ての答えを持っている必要はなく、多様な意見を引き出し、それをまとめ上げ、共に前に進むファシリテーターとしての役割を果たすことが重要になります。
モチベーションとエンゲージメントの測定方法
モチベーションとエンゲージメントは、どちらも従業員の心理的な状態や組織との関係性といった定性的な要素を含むため、その状態を正確に把握するためには適切な測定方法を用いる必要があります。
これらの要素を可視化し、定期的に測定することで、組織の現状を客観的に評価し、効果的な改善策を立案・実行することが可能になります。主な測定方法としては、サーベイの実施や、そこから得られるレポートの分析が挙げられます。
スコアリングの設計とサーベイの例
従業員のエンゲージメントやモチベーションを測定するためには、サーベイ(従業員調査)を実施し、その結果を数値化(スコアリング)する手法が広く用いられています。
エンゲージメントサーベイでは、組織への理解度、共感度、行動意欲といったエンゲージメントを構成する様々な要素に関する質問を設定し、従業員に回答してもらいます。
回答結果を事前に定めた基準に基づいて数値化することで、個人のエンゲージメントレベルや組織全体の傾向を把握できます。スコアリング設計においては、各質問項目がどのエンゲージメント構成要素に関連するのかを明確にし、総合的なエンゲージメントスコアだけでなく、要素別のスコアも算出できるようにすることが有効です。
例えば、「会社のビジョンに共感できるか」「自分の仕事が会社の成功に貢献していると感じるか」といった質問項目に対し、5段階や7段階のリッカート尺度で回答を得る形式などが一般的です。また、短期間で従業員の状況を把握するためのパルスサーベイも有効な手段です。
サーベイ結果を集計・分析し、レポートとしてまとめることで、組織全体の強みや弱み、改善すべき課題などを具体的に特定することができます。
エンゲージメントスコアとNPSの違い
エンゲージメントスコアとNPS(ネット・プロモーター・スコア)は、どちらも従業員の意識を測るためにサーベイを用いることがありますが、その焦点と目的には明確な違いがあります。
エンゲージメントスコアは、従業員が組織に対してどれだけ深く関与し、貢献意欲を持っているか、という「組織との関係性」や「仕事への熱意」に焦点を当てた指標です。
一方、NPSは「この職場を友人や知人にどの程度すすめたいか」という質問を通じて、従業員の「推奨意向」を測定する指標であり、顧客ロイヤルティ測定で用いられるNPSの考え方を従業員向けに応用したものです。
エンゲージメントスコアが組織への愛着や貢献意欲といった内面的な状態をより詳細に測るのに対し、eNPS(従業員向けNPS)は組織に対する総合的な評価や推奨度を簡易的に把握することに適しています。
どちらのサーベイも組織の状況を把握し、改善のためのレポート作成に繋がりますが、目的とする情報や得られるインサイトが異なります。
組織の活性化に向けた施策を検討する際には、これらの違いを理解し、目的に合った測定方法を選択することが重要です。
可視化ツールやレポート運用のポイント
モチベーションやエンゲージメントの測定結果を効果的に活用するためには、単に数値を把握するだけでなく、その結果を分かりやすく可視化し、継続的に運用していくことが重要です。
エンゲージメントサーベイなどで得られたスコアや従業員からのフィードバックを、ダッシュボードやグラフなどを活用して視覚的に表現することで、組織全体の傾向や部署ごとの特徴、経時的な変化などを直感的に把握できるようになります。
また、可視化ツールの中には、特定の要素間の相関関係を分析したり、改善優先度の高い課題を特定したりする機能を備えているものもあります。
レポートの運用においては、単に結果を関係者に共有するだけでなく、その結果に基づいて具体的なアクションプランを策定し、実行に移すことが不可欠です。
サーベイは一度きりで終わらせるのではなく、定期的に実施し、前回の結果と比較することで、施策の効果測定や新たな課題の発見に繋がります。
重要なのは、サーベイ結果をネガティブなものとして捉えるのではなく、組織改善のための貴重な情報として積極的に活用し、従業員へのフィードバックや対話を通じて、共に働く環境を良くしていこうという姿勢を示すことです。
これからの組織に求められる姿勢とは
予測困難な現代社会において、企業が持続的に成長するためには、従業員のモチベーションとエンゲージメントを両輪として捉え、これらを高めるための組織的な姿勢が不可欠です。
一方的な指示や管理ではなく、従業員一人ひとりと真摯に向き合い、「対話」を重ねる組織文化を醸成し、変化する働き方に合わせて組織と従業員の関係性を常に進化させていくことが求められます。
モチベーションとエンゲージメントは両輪
組織の持続的な成長と従業員の幸福度向上を実現するためには、モチベーションとエンゲージメントはどちらか一方だけではなく、まさに車の両輪のようにバランス良く高めていくべき重要な要素です。
モチベーションが高い従業員は、個々の業務に対して高い「やる気」とエネルギーを持って取り組み、生産性向上に貢献します。
一方、エンゲージメントが高い従業員は、組織のビジョンや価値観に共感し、組織の一員として貢献したいという強い意志を持ち、離職率の低下や組織全体の活性化に繋がります。
たとえ個人のモチベーションが高くても、組織への帰属意識や貢献意欲が低ければ、そのエネルギーが組織の目標達成に繋がりにくく、また、長期的な定着も期待できません。
逆に、組織へのエンゲージメントが高くても、個々の業務に対するモチベーションが低ければ、十分なパフォーマンスを発揮できない可能性があります。
したがって、これからの組織には、個人の「やる気」を引き出すモチベーション向上施策と、組織との「繋がり」を強化するエンゲージメント向上施策を組み合わせ、両方を相乗的に高めていく視点が不可欠です。
ロイヤリティといった概念も重要ですが、エンゲージメントが示す双方向の信頼関係と貢献意欲は、現代の多様な働き方において、より多くの従業員の心を掴む鍵となります。
この二つの要素の違いを理解し、組織全体で高める努力を続けることが、変化に強い組織を作る土台となります。
一方的でなく「対話」を重ねる組織文化の必要性
これからの組織において、従業員のモチベーションとエンゲージメントを高めるためには、経営層や管理職から従業員への一方的な指示や情報伝達だけでなく、「対話」を重視する組織文化を醸成することが不可欠です。
従業員が自身の意見や考えを自由に表現でき、それが組織運営に反映される機会があると感じられる環境は、従業員の主体性や参画意識を高め、「やる気」を引き出すことに繋がります。
例えば、定期的な1on1ミーティングを通じて、上司と部下が業務に関するフィードバックだけでなく、キャリアの悩みや個人的な価値観についても話し合う時間を設けたり、部署やチームの目標設定に従業員が主体的に関わる機会を作ったりすることが有効です。
また、全社的なタウンホールミーティングや少人数の座談会などを開催し、経営層と従業員が直接対話することで、相互理解を深め、組織への信頼感を高めることができます。
このような「対話」を重ねるプロセスを通じて、従業員は組織の一員として尊重されていると感じ、組織に対するエンゲージメントが強化されます。
モチベーションとエンゲージメントの違いを踏まえ、個人の「やる気」と組織との「繋がり」の両面に働きかけるためには、一方通行ではない双方向のコミュニケーションが鍵となります。
変化の激しい時代において、多様な視点を取り入れ、共に組織を創り上げていく「共創」の姿勢は、組織の適応力と競争力を高める上で非常に重要です。
働き方の変化とともに進化する関係性づくり
リモートワークやフレックスタイムなど、働き方が多様化する現代において、組織と従業員の関係性づくりも常に進化させていく必要があります。
画一的な管理や評価制度だけでは、多様な働き方をする従業員のモチベーションやエンゲージメントを維持・向上させることは難しくなってきています。
これからの組織には、従業員一人ひとりの状況や価値観を理解し、個別に寄り添う姿勢が求められます。
例えば、リモートワークで働く従業員に対しては、対面でのコミュニケーションが減る分、オンラインツールを活用したこまめな情報共有や、意図的な雑談の機会を設けるといった工夫が必要です。
また、フレックスタイム制度を利用する従業員に対しては、成果に基づいた評価をより重視するなど、時間や場所に捉われない働き方を尊重する評価制度の導入も有効でしょう。
働き方の変化に合わせて、組織のルールや制度を柔軟に見直し、従業員が「この会社で自分らしく働ける」と感じられる環境を整備することが、エンゲージメントを高める鍵となります。
重要なのは、組織が一方的に「働き方を提供する」のではなく、従業員と共に理想の働き方や組織のあり方を考え、対話を重ねながら関係性を築いていくことです。このように、働き方の変化に対応し、従業員との関係性を進化させていく姿勢が、これからの組織には不可欠となります。
まとめ:エンゲージメントとモチベーションの理解が組織力強化の鍵
本記事では、モチベーションとエンゲージメントのそれぞれの概念、両者の違い、重要性、そして高めるための具体的な施策と測定方法について解説しました。
モチベーションが個人の「やる気」や「意欲」といった内面的な動機に焦点を当てているのに対し、エンゲージメントは組織と従業員との「心理的な結びつき」や「貢献意欲」といった双方向の関係性を指します。
これら二つの要素は異なる概念でありながらも、互いに影響し合う密接な関係にあり、どちらか一方だけではなく、両方をバランス良く高めていくことが組織力強化の鍵となります。
従業員のモチベーションを高めることで、個々のパフォーマンスや生産性の向上が期待でき、エンゲージメントを高めることで、従業員の定着率向上や組織全体の活性化に繋がります。
エンゲージメントとモチベーションの違いを理解し、成果連動型の報酬やキャリア設計支援、ポジティブフィードバックといったモチベーション向上施策などエンゲージメント向上施策を組み合わせ、従業員一人ひとりと組織のより良い関係性を築いていくことが、変化の激しい時代を乗り越え、持続的に成長していく組織にとって不可欠と言えるでしょう。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。